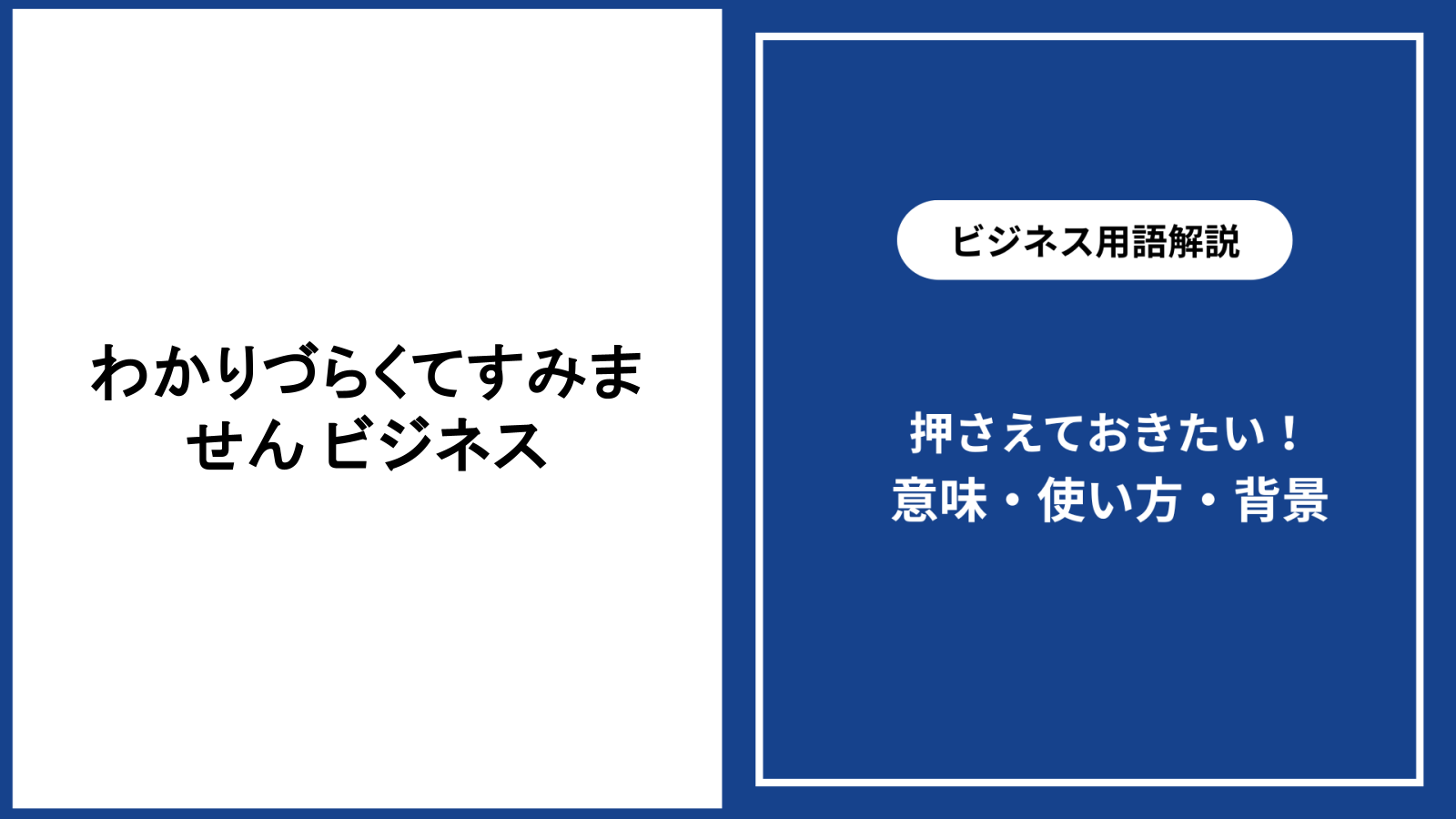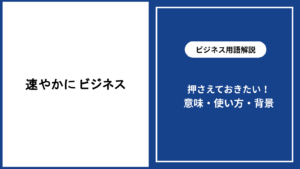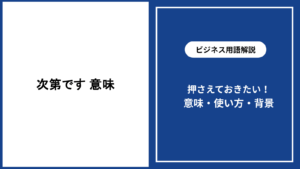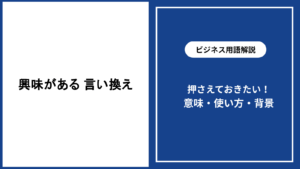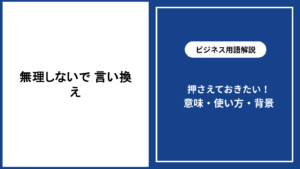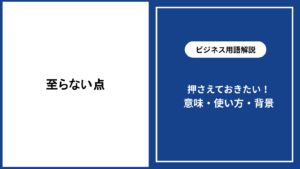ビジネスシーンでよく耳にする「わかりづらくてすみません」。
このフレーズを使うとき、どんな意図や配慮が込められているのでしょうか。
この記事では、「わかりづらくてすみません」の意味や正しい使い方、似た表現との違い、さらにはビジネスメールや会話での活用例まで、分かりやすく解説します。
今すぐ実践できるポイントも豊富にご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
わかりづらくてすみませんとは
「わかりづらくてすみません」は、自分の説明や資料、発言が相手にとって理解しにくい場合に用いる謝罪表現です。
特にビジネスの現場では、相手への配慮や誠実さを示すために使われることが多く、相手に不便をかけたことを丁寧に詫びる気持ちが込められています。
この表現は、相手の理解度に寄り添う姿勢を示せるため、コミュニケーション力の高さや信頼感を印象づけるのにも役立ちます。
また、メールや会議など様々なビジネスシーンで活用されている便利な言い回しです。
どんな場面で使うのか
「わかりづらくてすみません」は、説明資料を提出した際や会議・商談の場で、内容が複雑だったり情報量が多かったりして、相手から質問や確認が入ったときによく使われます。
例えば、「この部分の意味がよく分からなかったのですが」と指摘された場合に、「わかりづらくてすみません、補足いたします」と返すことで、相手の疑問に真摯に応じる姿勢を示せます。
また、メールやチャットで複数の情報を一度に伝える際にも、「わかりづらくてすみません、何かご不明点があればご指摘ください」と添えることで、相手が質問しやすい雰囲気を作ることができます。
ビジネスシーンでの正しい使い方
ビジネスの場では、単に謝罪するだけでなく、「わかりづらくてすみません」に続けて、どの点が分かりにくかったのかを具体的に聞いたり、説明を加えたりすることが大切です。
例えば、「わかりづらくてすみませんでした。どの部分がご不明でしたでしょうか?」や、「わかりづらくてすみません、補足資料をお送りします」といった具合です。
これにより、単なる謝罪にとどまらず、相手との信頼関係を築いたり、円滑なコミュニケーションにつなげたりすることができます。
また、何度も同じ表現を繰り返すと印象が悪くなる場合もあるため、適度な使用と表現のバリエーションを意識しましょう。
似た意味の表現や言い換え例
「わかりづらくてすみません」と同じような意味で使える表現には、「説明が不十分で申し訳ありません」「ご説明が至らず失礼いたしました」「ご不明点がございましたらご指摘ください」などがあります。
状況や相手との関係性に応じて、より丁寧な言い回しや柔らかい表現を選ぶことで、印象を良くすることも可能です。
また、英語で伝える場合は、「Sorry for the confusion」や「I apologize for not being clear」などが一般的です。
言い換え表現を使い分けることで、文章や会話にバリエーションを持たせることができます。
ビジネスメール・会話での実践例
ビジネスメールや日常の会話で「わかりづらくてすみません」をどのように使えば良いのでしょうか。
ここでは実際のシーンを想定しながら、自然で効果的な使い方を詳しく解説します。
メールでの使い方
ビジネスメールでは、説明がややこしい内容や複雑な資料を送る際に、「わかりづらくてすみません」を添えることで、相手への配慮を示すことができます。
例えば、「下記の通りご案内いたしますが、分かりづらい点がございましたら何なりとお申し付けください」など。
また、指摘や質問を受けた場合には、「先ほどのご説明がわかりづらくてすみません、補足いたします」と返信することで、誠意が伝わります。
こうした一文を添えるだけで、相手との関係性がより円滑になるでしょう。
会議や商談での使い方
会議や商談の場では、発言内容が複雑になった場合や、参加者から質問が出た際に、「わかりづらくてすみません」と口頭で加えると、場の雰囲気が和らぎます。
「ご説明がわかりづらくてすみません。もう一度詳しくご説明いたします」や、「もしご不明点があれば、何でもご質問ください」と言うことで、相手に安心感を与えられます。
また、初対面の相手や年上の方に対しては、より丁寧な「ご説明が至らず申し訳ありません」という表現にするとより良いでしょう。
電話応対での使い方
電話やオンライン会議でも、「わかりづらくてすみません」は有効です。
口頭だと相手の反応が見えにくいため、「もし説明がわかりづらければ、遠慮なくおっしゃってください」と前置きすることで、相手が質問しやすくなります。
また、説明の途中で相手が戸惑った様子を見せた場合には、「わかりづらくてすみません、もう一度ご説明いたします」とすぐにフォローを入れると信頼感が高まります。
電話では声のトーンや話し方も大切なので、ゆっくりと丁寧に話すことも心がけましょう。
使う際の注意点とポイント
「わかりづらくてすみません」を使う上で、注意すべきポイントや、より効果的に伝えるコツを押さえておきましょう。
謝罪だけで終わらせず、次のアクションにつなげることが大切です。
謝罪だけで終わらないフォローが重要
「わかりづらくてすみません」と謝罪した後は、具体的にどの部分が分かりづらかったのかを把握し、改善や補足説明を行うことが求められます。
相手がどの点でつまずいたのかを確認し、積極的に「どの点がご不明でしたでしょうか?」や「ご説明を追加いたします」と続けることで、実務的な信頼を得やすくなります。
また、同じミスや分かりづらさを繰り返さないよう、説明や資料の作り方を見直すことも重要です。
これにより、今後のコミュニケーションの質が向上します。
使いすぎに注意しよう
便利な表現ですが、何度も繰り返し使いすぎると「説明が下手な人」「配慮が足りない人」と思われる危険性もあります。
一度の会話やメールで何度も同じ謝罪をするのは避け、必要に応じて言い換えたり、説明自体を分かりやすくする工夫が求められます。
また、「すみません」よりも「申し訳ありません」「失礼いたしました」など、より丁寧な表現を場面によって使い分けることも好印象につながります。
前向きな姿勢を見せる
謝罪の言葉だけでなく、「今後、より分かりやすいご説明を心がけます」や「次回からは資料を簡潔にまとめます」など、改善への意欲を示すことで、評価がアップします。
ビジネスパーソンとして成長を感じさせる一言を添えると、相手からの信頼度も高まります。
また、「何かご不明点がございましたら、いつでもご連絡ください」といった前向きなフォローを加えるのもおすすめです。
まとめ
「わかりづらくてすみません ビジネス」は、相手への配慮や誠実さを伝えるための大切なフレーズです。
ビジネスメールや会話、電話応対など様々なシーンで効果的に使い分けることで、信頼関係の構築やコミュニケーションの円滑化に役立ちます。
ただし、謝罪だけで終わらず、フォローや説明の追加、今後の改善点を明確に伝えることが重要です。
適切に使い分けて、より良いビジネスコミュニケーションを目指しましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 使う場面 | 説明や資料が分かりにくかった場合の謝罪として |
| 注意点 | 謝罪だけで終わらず具体的なフォローや改善を示す |
| 表現のバリエーション | 「ご説明が至らず申し訳ありません」「ご不明点がございましたらご指摘ください」など |
| 前向きな姿勢 | 今後の改善やサポート姿勢を積極的に示すことが大切 |