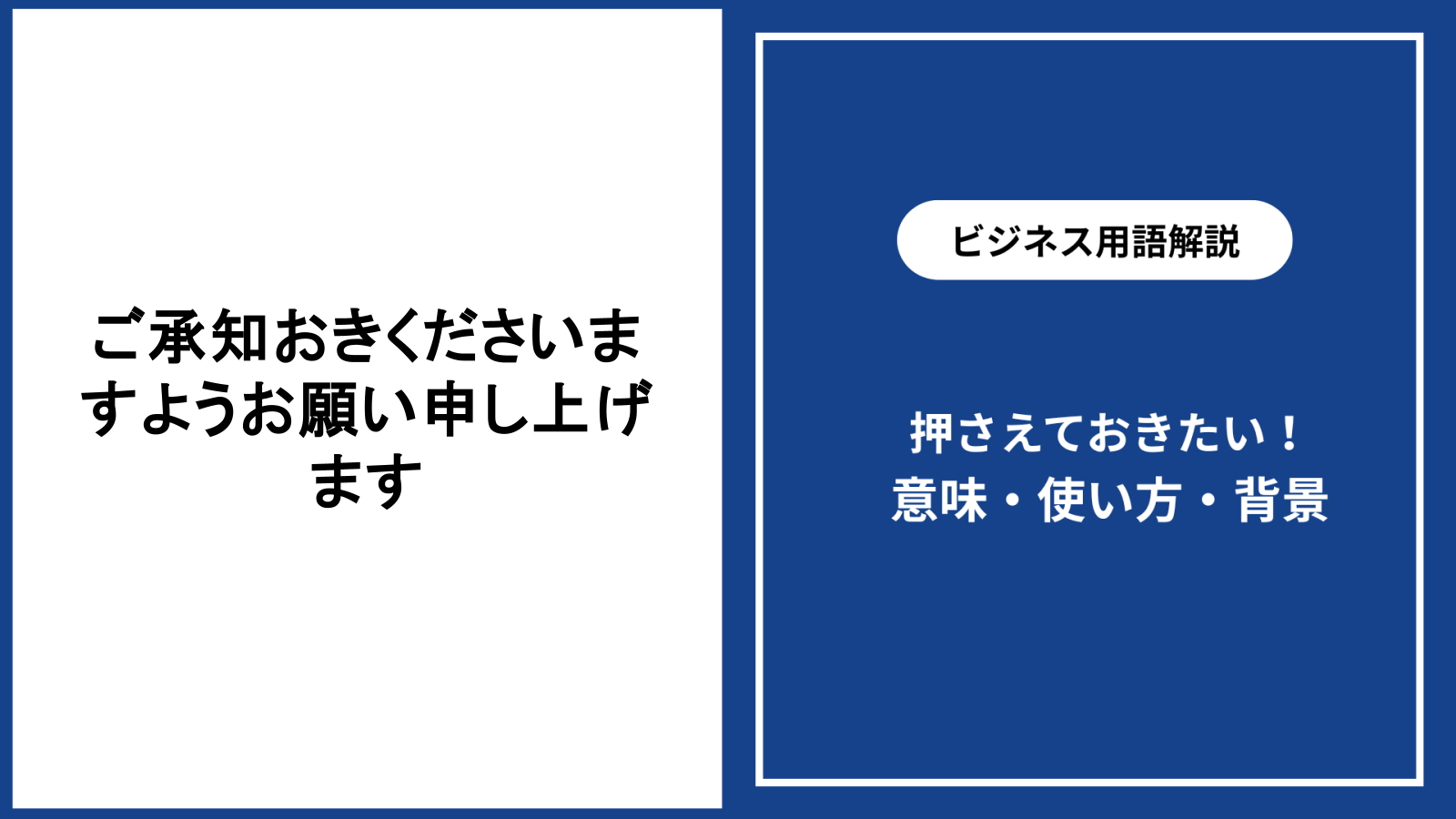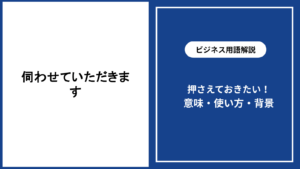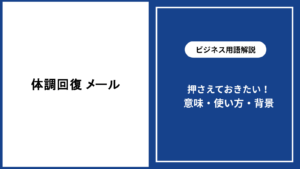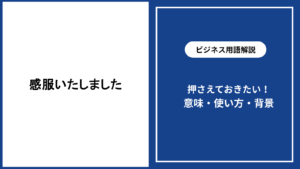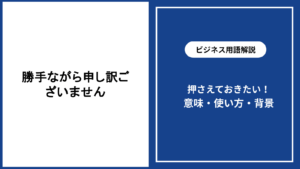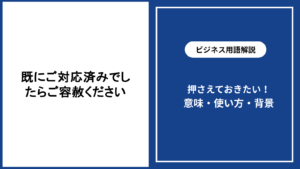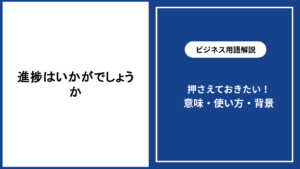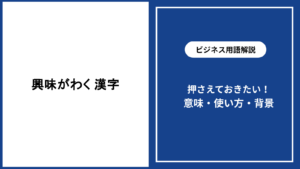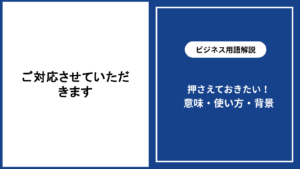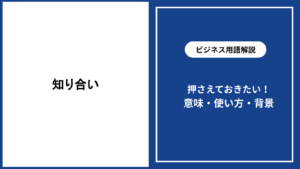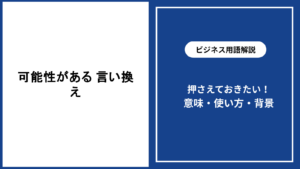ビジネスメールや書面で頻繁に使われる「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」。
このフレーズは、相手に「知っておいてください」という丁寧な表現ですが、どんな場面で使うのが正しいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ご承知おきくださいますようお願い申し上げますの正しい意味や使い方、類似表現との違い、実際のビジネスシーンにおける例文まで、分かりやすく徹底解説します。
ご承知おきくださいますようお願い申し上げますの基本的な意味
このフレーズは、相手に何かを理解・把握しておいてほしいときに使われる、非常に丁寧な依頼表現です。
「ご承知おき」とは「事情や内容をあらかじめ知っておいてください」という意味で、「くださいますようお願い申し上げます」と続けることで、より丁寧で謙虚なニュアンスになります。
ビジネス文書やメール、通知文、案内状など、フォーマルな場面でよく用いられます。
特に、相手に対して把握や理解を依頼しつつ、敬意を表したいときに最適です。
単なる「ご承知おきください」よりも、さらに丁重な表現であり、目上の人や取引先など、フォーマルな相手に対して失礼のない言い回しとなっています。
「ご承知おき」の語源と意味
「ご承知おき」は、「承知しておく」の尊敬語です。
「承知」とは、ある事柄を理解し、納得していることを意味します。
ここに「おき」がつくことで、あらかじめ知っておいてほしい、先んじて理解していてほしい、というニュアンスが含まれます。
たとえば、社内規定の変更や業務フローの改定など、今後の仕事に関わる情報を伝える際に「ご承知おきください」と使われます。
「ご承知おき」は事前の注意喚起や周知に最適な表現であり、相手の理解や把握を促す役割があります。
そのため、指示や命令ではなく、依頼やお願いのニュアンスを大切にしたい場合に使われます。
「くださいますようお願い申し上げます」の丁寧さ
「くださいますようお願い申し上げます」は、相手の行為をお願いする際に使う、非常に丁重な依頼表現です。
「くださいます」は「くださる」の尊敬語、「お願い申し上げます」は「お願いします」の謙譲語で、どちらも相手への敬意を強調します。
このひとことを付け加えることで、依頼の内容がより丁寧になり、固い印象を与えます。
お客様や取引先、上司など、失礼のない文章を心掛けたい相手に対して用いるのが適切です。
ビジネスメールや正式な書面での使用に非常に適しています。
使う場面と注意点
「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」は、情報提供や注意喚起、案内など、相手に対して知っておいてほしいことを丁寧に伝えたいときに使います。
例えば、スケジュール変更やルールの改定、重要な連絡事項を案内するときなどが典型です。
ただし、命令や強制的なニュアンスを避けたい場合に選ぶ言葉なので、指示や命令をしたいときには不向きです。
また、カジュアルな場面や親しい間柄ではやや堅苦しく感じられるため、使い分けが重要です。
ご承知おきくださいますようお願い申し上げますの正しい使い方
ここでは、この表現をどのようなビジネスシーンで使うべきか、またメールや文書での具体的な使い方について詳しく解説します。
敬語表現に自信がない方も安心して使えるよう、ポイントを押さえておきましょう。
ビジネスメールでの使い方
「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」は、ビジネスメールで非常によく使われる表現です。
たとえば、会議日時の変更、納期の遅延、新しい部署体制の案内など、相手にあらかじめ認識しておいてほしい内容を伝える場合に用います。
以下のような文末で使うと、自然で丁寧な印象になります。
例:「本件につきましては、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
また、「ご多用のところ恐れ入りますが」「何卒よろしくお願い申し上げます」といったクッション言葉と組み合わせることで、より柔らかな印象を与えることができます。
社内・社外文書での例文
社内の掲示や通知文、社外への案内状など、書面での使用も一般的です。
たとえば、就業規則の改定、手続きの変更、設備工事のお知らせなど、関係者全員に知っておいてほしい事項を伝える際に使います。
例:「来月より新しい出勤システムを導入いたしますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このように、あらかじめ相手に周知・理解を求める際に、フォーマルな場面で活用できます。
誤用・避けたい使い方
「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」は、あくまでお願い・依頼の表現です。
そのため、相手に何か作業や行動を依頼したい場合には、誤用となるので注意しましょう。
例えば、「提出をお願いします」「ご確認をお願いします」と言いたい場面で「ご承知おき」と使うと、意味が通じなくなることがあります。
「ご承知おき」は「知っておいてください」という意味であり、行動や作業そのものを依頼する言葉ではありません。
類似表現との違い・使い分け
「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」には、似た意味を持つ表現がいくつか存在します。
ここでは、代表的な類語との違いと、使い分けのポイントについて解説します。
「ご確認ください」との違い
「ご確認ください」は、相手に対して「内容を実際にチェックしてほしい」ときに使う表現です。
一方、「ご承知おきください」は「ただ知っておいてほしい」「把握しておいてほしい」というニュアンスになります。
「ご確認ください」はアクション(確認)を求める表現、「ご承知おきください」は認識のみを求める表現です。
そのため、内容をしっかり確かめてほしい場合は「ご確認ください」、情報共有や周知のみで良い場合は「ご承知おきください」を使いましょう。
「ご了承くださいますようお願い申し上げます」との違い
「ご了承」とは、「事情を理解して受け入れてください」という意味があります。
つまり、相手の納得や承諾を求めるニュアンスが強い言葉です。
対して「ご承知おきください」は、納得や承諾までは求めず、ただ「知っておいてください」と伝える表現です。
「ご了承」は承諾の依頼、「ご承知おき」は周知の依頼と覚えておくと、ビジネスメールでの使い分けがしやすくなります。
「ご案内申し上げます」との違い
「ご案内申し上げます」は、何かをお知らせするときに使う表現です。
具体的な内容やイベントなどを紹介・通知する場合に適していますが、相手に知っておいてほしいときだけでなく、案内そのものを目的とする場面で使われます。
周知・認識を促したいときは「ご承知おき」、単に情報を知らせたいときは「ご案内」と使い分けると良いでしょう。
ビジネスシーンでの使い方と例文
実際のビジネスメールや社内文書での「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」の活用例を具体的に紹介します。
状況に合わせて表現をアレンジできるよう、例文を参考にしてください。
案内・通知メールでの例文
「来月1日より、オフィスの入館システムが変更となります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このようにシステムやルールの変更、イベントの詳細通知など、相手にあらかじめ知っておいてもらいたい内容を伝える際に最適です。
「本プロジェクトの進捗状況につきましては、毎週金曜日にご報告いたしますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このような一文を添えることで、相手に安心感や信頼感も与えられます。
取引先へのフォーマルな連絡
「誠に恐縮ではございますが、年度末の棚卸作業に伴い、出荷スケジュールが一部変更となります。
ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このように、相手に対してご迷惑をおかけする場合や、不便をかける内容を伝える際にも使われます。
「弊社の担当部署が変更となりましたので、今後のお問い合わせは新担当までお願い申し上げます。
何卒ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このように、今後の連絡や対応が変わる場合にも、丁寧に伝えることができます。
社内連絡・通達での使い方
「来週よりオフィス内の空調工事を実施いたします。
作業中はご迷惑をおかけすることもございますが、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このように、社員や関係者全員に対して注意喚起や事前案内をしたい場合に活用できます。
「新年度より、出勤時の健康チェックが義務付けられます。
ご協力のほど、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。」
このような社内周知メールにも最適です。
まとめ:ご承知おきくださいますようお願い申し上げますの使い方を正しく理解しよう
「ご承知おきくださいますようお願い申し上げます」は、相手に敬意を示しながら、情報や事情を知っておいてほしいと依頼する最上級の丁寧表現です。
ビジネスメールや通知、案内状、社内外の連絡文書で頻繁に用いられ、相手に失礼のない文章を作りたいときに非常に役立ちます。
似たような表現との違いや、使い分けのポイントを押さえておけば、より的確かつスマートなコミュニケーションが可能になります。
ぜひ本記事を参考に、正しい場面・正しい意味でご承知おきくださいますようお願い申し上げますを使いこなしてください。
| 表現 | 意味・使い方 |
|---|---|
| ご承知おきくださいますようお願い申し上げます | 相手に事情や情報を知っておいてほしいときの最上級の丁寧な依頼表現 |
| ご確認ください | 内容を実際にチェックしてほしい場合に使う |
| ご了承くださいますようお願い申し上げます | 受け入れと承諾をお願いするときに使う |
| ご案内申し上げます | 何かをお知らせしたいときに使う |