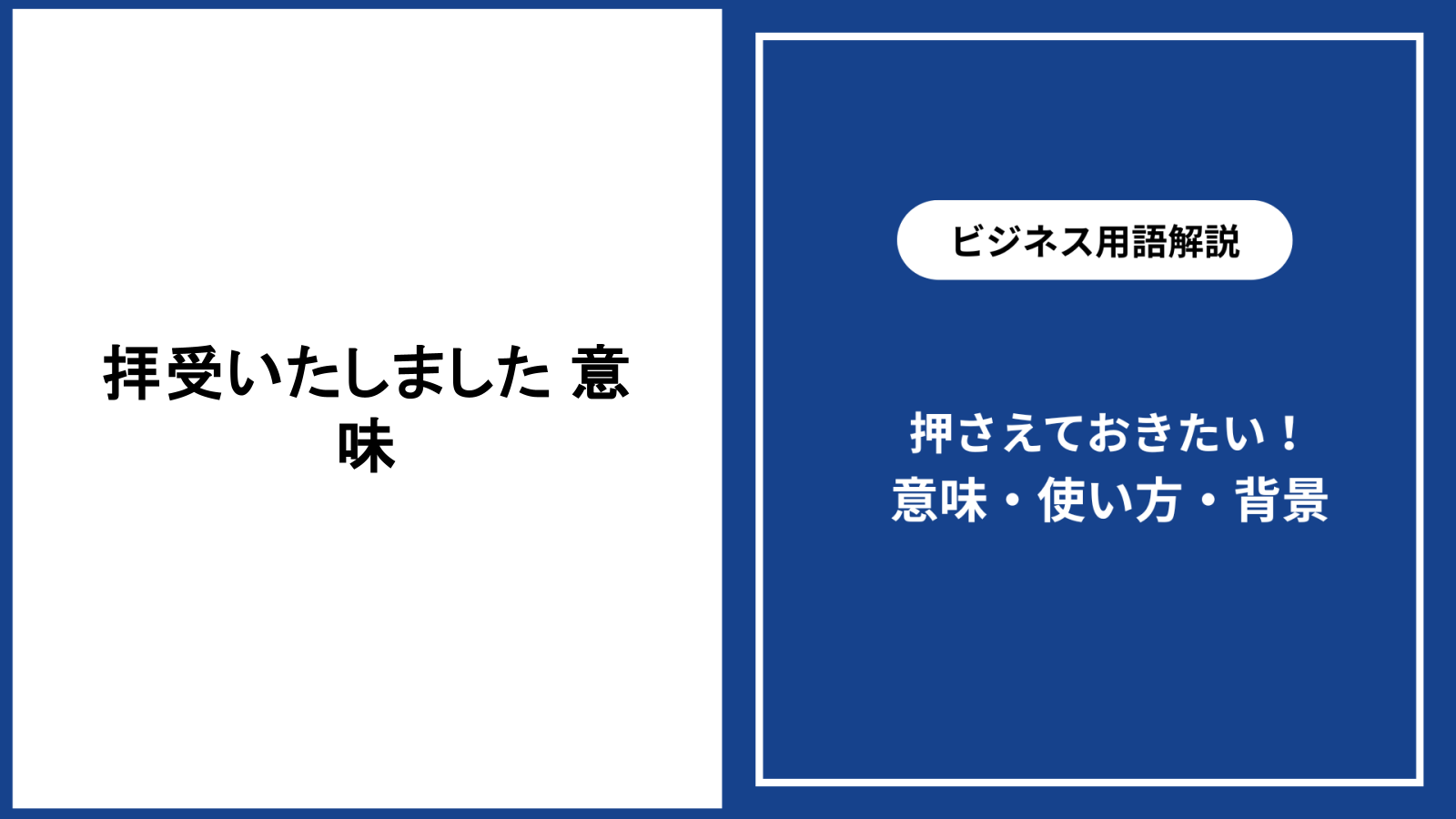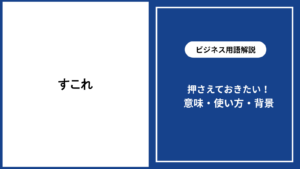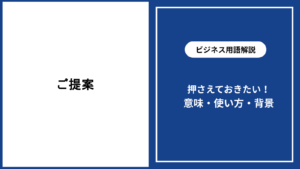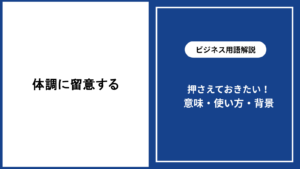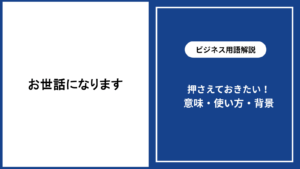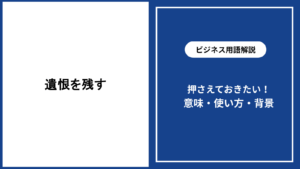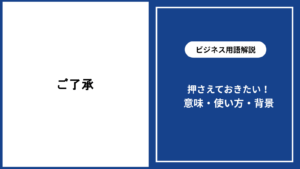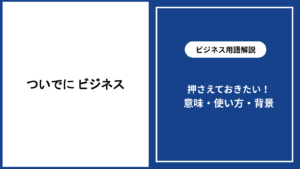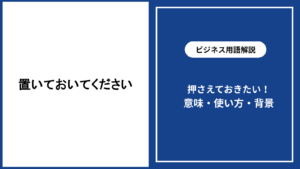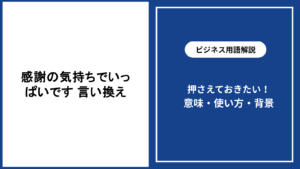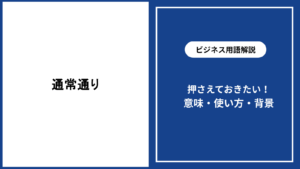ビジネスメールや手紙で頻出する「拝受いたしました」ですが、正しい意味や使い方を理解している方は意外と少ないかもしれません。
この記事では、「拝受いたしました」の意味や読み方、例文、類語、間違いやすいポイントまで詳しくご説明します。
「拝受いたしました」を使いこなしたい方、メールのマナーを身に付けたい方におすすめの内容です。
拝受いたしました 意味と読み方
「拝受いたしました」は、相手から送られたものを「謹んで受け取りました」という意味を持つ敬語の表現です。
ビジネスやフォーマルな場面で、資料やメール、書類、贈り物などを受け取った際に使われます。
このフレーズは丁寧な日本語表現のひとつで、社会人として知っておきたい基本的な言い回しです。
読み方は「はいじゅいたしました」です。
漢字で書くと少し難しく見えますが、意味を理解すると使いやすくなります。
「拝」は「謹んで」という意味合いを持ち、「受」は「受け取る」、「いたしました」は「する」の謙譲語表現です。
「拝受」の語源と構造
「拝受」は、「拝(つつしんで)」+「受(受け取る)」の二つの漢字から成り立っています。
「拝」は相手に対して敬意を表す漢字で、主に手紙やメールなど書き言葉で使われます。
「受」はそのまま「受け取る」という意味です。
「いたしました」が加わることで、より謙譲語としての丁寧さが増します。
この表現は自分がへりくだって相手への敬意を示す際に使うため、目上の人や取引先などフォーマルな関係性で用いられるのが一般的です。
カジュアルな場面や親しい間柄で使うと違和感を持たれることが多いので注意しましょう。
ビジネスメールでの「拝受いたしました」の使い方
ビジネスメールにおいて「拝受いたしました」は、書類・資料・メール・贈答品などを受け取ったことを正式に伝える際に使用されます。
例えば、取引先から送付された書類やデータ、請求書などを受領した時に「確かに受領いたしました」よりも丁寧な印象を与えることができます。
メール本文では、「資料を拝受いたしました」や「ご送付いただきました書類を拝受いたしました」のように使います。
この表現を使うことで、相手に対して敬意と感謝の気持ちをきちんと伝えることができます。
特に初対面や目上の方、重要な取引先などに使うと好印象です。
「拝受いたしました」を使う際の注意点
「拝受いたしました」は非常に丁寧な表現ですが、使う場面や相手を選ぶ必要があります。
例えば、社内の目下の方や親しい同僚との会話で使うと、かえって堅苦しい印象を与えてしまうことがあります。
また、受け取ったものが明確な場合にのみ使うのが適切ですので、内容が曖昧な場合は「受領いたしました」など他の表現を使いましょう。
また、「拝受」と「いたしました」を重ねているため、これ以上謙譲語や丁寧語を重ねると過剰な敬語になる恐れがあります。
「拝受させていただきました」とは言わないよう注意しましょう。
拝受いたしましたの例文・使い方
実際のビジネスメールや手紙でどのように「拝受いたしました」を使えば良いのか、例文で確認しましょう。
ここでは、様々なシーンに合わせた使い方を紹介します。
ビジネスメールでの例文
・ご送付いただきました資料を拝受いたしました。
・先ほどメールにてお送りいただいたファイルを拝受いたしました。
・ご依頼いただきました見積書を確かに拝受いたしました。
これらの例文のように、「何を」「どのように」受け取ったかを明記することで、より丁寧に伝えることができます。
また、受領した旨だけでなく、「今後の対応」や「感謝の気持ち」も一緒に添えると、より誠実な印象を与えられます。
例えば、「ご送付いただきました書類を拝受いたしました。早速、内容を確認しご連絡申し上げます。」などのように続けると良いでしょう。
手紙や書類の受領連絡での使い方
手紙や贈答品など、書類以外の受領連絡にも「拝受いたしました」は使えます。
例えば、「ご恵贈いただきました品を拝受いたしました」や「ご案内状を拝受いたしました」などが代表的です。
贈り物や案内状、招待状などを受け取った際にも活用できるので、覚えておくと大変便利です。
特に、目上の方や重要な取引先からの書面や贈答品に対して、失礼のない表現として重宝します。
この場面では、受け取ったことを丁寧に伝えることで、相手に安心感や信頼感を与えることができます。
社外とのやり取りでの正しい使い方
社外の取引先や顧客とのやり取りで「拝受いたしました」を使うと、相手に対して最大限の敬意を示すことができます。
社外メールでは、特に「○○を拝受いたしました。誠にありがとうございます。」のように、感謝の気持ちを添えるとより丁寧です。
また、書類や資料の受領確認だけでなく、申込書や契約書、案内状、贈答品など、幅広いシーンで使える便利な表現です。
ただし、あくまでもフォーマルな場面に限り使用し、社内や目下の相手、カジュアルなやり取りでは避けるようにしましょう。
「拝受いたしました」を正しく使い分けることで、ビジネスパーソンとしての信頼度がアップします。
拝受いたしましたの類語・言い換え表現
「拝受いたしました」と同じような意味を持つ表現や、場面に応じた言い換えフレーズも覚えておくと便利です。
使い分け方やニュアンスの違いも合わせて解説します。
「受領いたしました」との違い
「受領いたしました」は「受け取りました」という意味で、「拝受いたしました」よりも少しカジュアルな表現です。
「受領」はビジネスシーンでよく使われる言葉ですが、「拝受」と比べると敬意の度合いはやや控えめです。
社内や同等の立場の相手、日常的な取引先とのやり取りでは「受領いたしました」で十分です。
一方で、特に目上の相手や重要な取引先には「拝受いたしました」を選ぶと、より丁寧な印象を与えることができます。
状況や相手によって適切な表現を選びましょう。
「確かに受け取りました」との違い
「確かに受け取りました」は、口語的でカジュアルな言い回しです。
メールやチャットなどで気軽に使える一方、フォーマルなビジネスメールや公式文書には不向きです。
例えば、社内のやり取りや親しい相手との間で「資料を確かに受け取りました」と使うのは問題ありませんが、外部の重要な相手には「拝受いたしました」や「受領いたしました」を使うほうが適切です。
その他の言い換え表現
他にも「頂戴いたしました」「承りました」なども受け取りの意を伝える表現です。
「頂戴いたしました」は、贈り物やお土産など物品の受け取りによく使います。
「承りました」は、依頼や要件などを受け付けた際に使う言葉で、書類や物品の受領にはあまり適しません。
それぞれの表現には使えるシーンやニュアンスがありますので、相手や場面に合わせて適切に選ぶことが大切です。
| 表現 | 使う場面 | 敬意の度合い |
|---|---|---|
| 拝受いたしました | フォーマル・目上・社外 | 非常に高い |
| 受領いたしました | ビジネス・社内外 | 高い |
| 確かに受け取りました | カジュアル・親しい間柄 | 普通 |
| 頂戴いたしました | 贈り物・物品 | 高い |
| 承りました | 依頼・要件 | 高い |
拝受いたしましたの正しい使い方とマナー
「拝受いたしました」は正しい場面で使うことが大切です。
ここではビジネスシーンでのマナーや注意点を解説します。
目上・取引先に使う場合
「拝受いたしました」は、特に目上の方や重要な取引先に使うのが適しています。
例えば、初めての取引や大切な契約書類の受領連絡など、失礼があってはいけないシーンで積極的に使いましょう。
この表現を使うことで、相手に対する敬意や感謝の気持ちをしっかりと伝えることができます。
メールの冒頭や締めくくりに「拝受いたしました」と記載することで、フォーマルな印象を与えられます。
社内や目下の相手に使う場合
社内や自分より目下の相手に「拝受いたしました」を使うと、やや堅苦しく、距離感を感じさせてしまうことがあります。
このような場合は「受領いたしました」や「確かに受け取りました」といった表現が適切です。
適切な敬語を使い分けることが、社内コミュニケーションの円滑化や信頼関係の構築につながります。
目上・目下、社内外で表現を使い分けることで、よりスマートなビジネスパーソンを目指しましょう。
メールや手紙でよくある間違い
「拝受させていただきました」や「拝受いたしましたのでございます」など、過剰な敬語にならないよう注意が必要です。
「拝受」と「いたしました」で既に十分な敬意が込められているため、これ以上敬語を重ねる必要はありません。
また、受け取った内容がはっきりしていない場合や、カジュアルなメールで使うと違和感を持たれることもあります。
適切な表現を心がけて、相手に不快感を与えないようにしましょう。
まとめ:拝受いたしましたの意味と使い方をマスターしよう
「拝受いたしました」は、ビジネスやフォーマルな場面で「謹んで受け取りました」と伝える最上級の敬語表現です。
正しい意味や使い方、類語との違いを理解し、場面や相手に合わせて使い分けることが大切です。
丁寧な表現を身に付けることで、ビジネスマナーやコミュニケーションの質が向上します。
ぜひ日々のメールや手紙で「拝受いたしました」を正しく活用し、相手に敬意を伝えましょう。