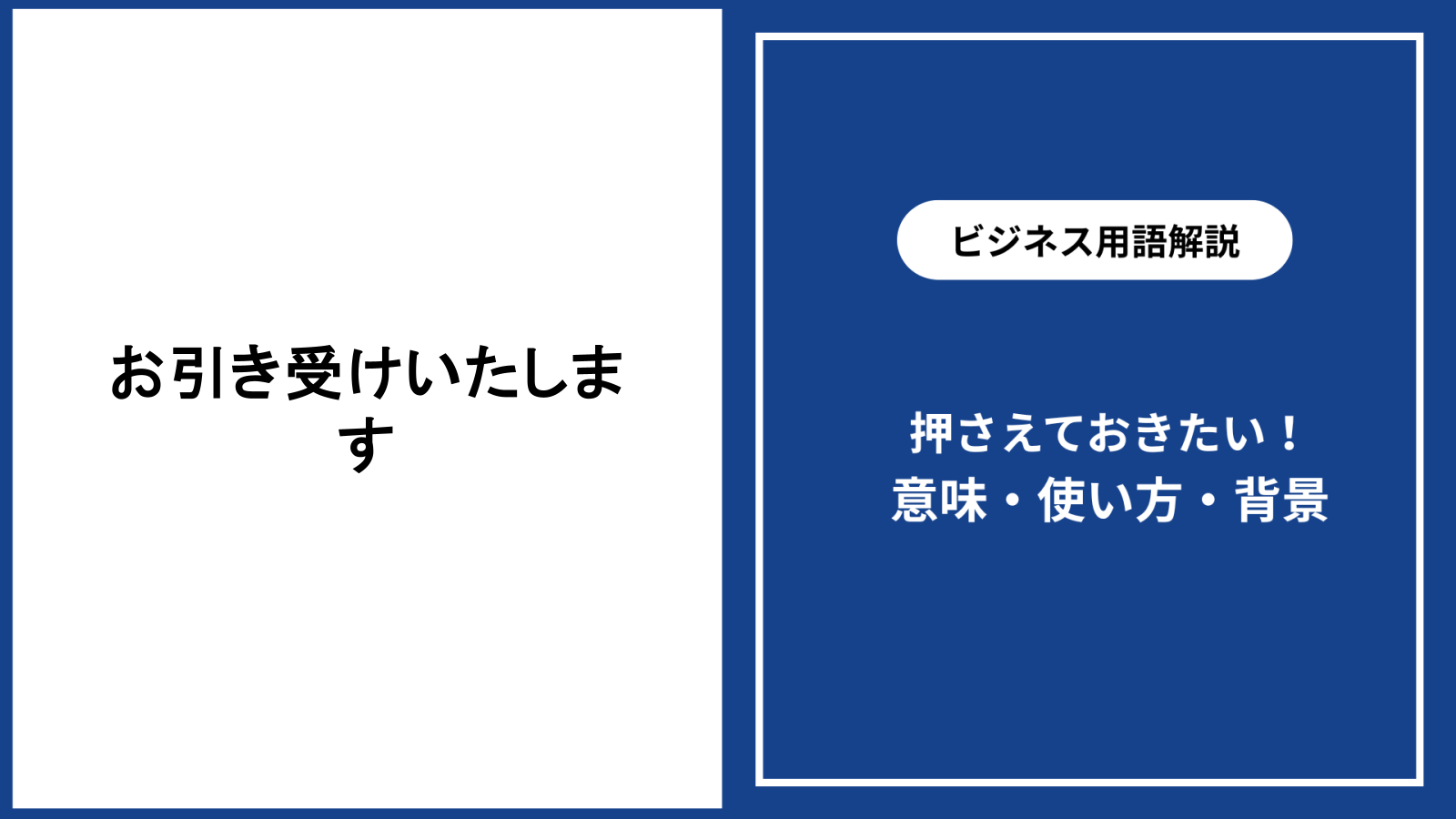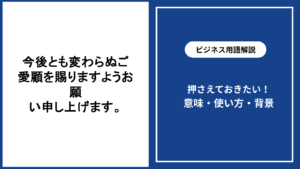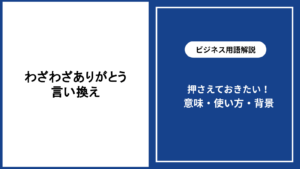「お引き受けいたします」はビジネスシーンで頻繁に使われる表現です。
取引先やお客様からの依頼や申し出に対して、丁寧に承諾の意を伝える際に使われます。
本記事では、「お引き受けいたします」の意味や正しい使い方、例文、類語や注意点まで、詳しく解説します。
敬語表現が苦手な方も、この記事を読めば安心して使いこなせるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
ビジネスメールや電話対応など、あらゆるコミュニケーションの場面で活躍する「お引き受けいたします」。
正確な意味やニュアンスを理解し、適切な場面で自信を持って使うためのポイントをまとめました。
お引き受けいたしますの意味と基本
この章では、「お引き受けいたします」という言葉の基本的な意味や成り立ち、使用場面についてご紹介します。
ビジネス敬語としての重要性も押さえておきましょう。
お引き受けいたしますの意味・語源
「お引き受けいたします」は、「引き受ける」に丁寧語と謙譲語を組み合わせた表現です。
相手からの依頼や申し出などを、自分が責任を持って承諾し実行することを丁寧に表す表現です。
「お引き受けします」よりも、さらに丁重なニュアンスがあり、ビジネスシーンで使うことで礼儀正しさや誠意を伝えることができます。
「いたします」は「する」の謙譲語であり、目上の人や取引先など、敬意を払う相手に適した表現です。
依頼や注文、業務の委託など、責任を持って遂行する意思を伝えるための敬語として広く使われています。
使う場面と適切なタイミング
「お引き受けいたします」は、仕事の依頼や業務委託、問い合わせ対応、予約や注文など、幅広いビジネスシーンで活躍する表現です。
特に、メールや電話、対面でのやりとりにおいて、相手からの要望や希望を快く受け入れる際に使用されます。
また、社内外問わず、上司やお客様、取引先など、丁寧な対応が求められる相手に対して使うことで、信頼感や安心感を与えることができます。
ただし、カジュアルな場面や親しい間柄では、やや堅苦しく感じられる場合もあるため、状況に応じて使い分けましょう。
お引き受けいたしますの正しい敬語レベル
「お引き受けいたします」は、敬語の中でも謙譲語に分類されます。
自分が行うことをへりくだって表現することで、相手に対する敬意を強調します。
「お引き受けします」よりもワンランク上の丁重な表現であり、ビジネスメールや重要なやりとりでよく使われます。
「承知いたしました」「承りました」などと同じく、社会人として押さえておきたい基本的な敬語表現です。
相手の依頼に対して、責任感や信頼感を持って対応する姿勢を示すことができるので、積極的に使えるようにしましょう。
お引き受けいたしますの使い方と例文
ここでは、「お引き受けいたします」を実際に使う際のポイントや、メール・電話・会話での具体的な例文をご紹介します。
場面ごとの使い分けを身につけて、より自然に敬語を使いこなしましょう。
ビジネスメールでの例文・使い方
ビジネスメールでは、依頼内容に対して丁寧に承諾の意を伝えるため、「お引き受けいたします」はとても便利です。
例えば、「ご依頼いただきました件、喜んでお引き受けいたします」や、「新規プロジェクトのご担当をお引き受けいたします」などが挙げられます。
また、メールの文末や挨拶文として用いることで、相手への配慮や信頼感をアピールできます。
「本件につきましては、責任を持ってお引き受けいたしますので、何卒よろしくお願いいたします」といった表現もよく使われます。
電話応対・口頭での使い方と注意点
電話や対面でのやりとりでも、「お引き受けいたします」は非常に重宝します。
例えば、お客様からの注文や要望に対して「かしこまりました。お引き受けいたします」と返答することで、丁寧かつ誠実な印象を与えられます。
ただし、口頭ではやや堅い印象を与える場合もあるため、相手との関係や状況に応じて「承知いたしました」「承ります」など他の表現と使い分けることも大切です。
また、相手の依頼をきちんと理解した上で使うよう心掛けましょう。
間違いやすい使い方・避けるべき表現
「お引き受けいたします」は、正しい敬語表現ですが、使い方を間違えると不自然になってしまうこともあります。
例えば、「お引き受けさせていただきます」といった二重敬語は、過剰な丁寧さになりやすく、ビジネスマナー上は避けた方が良いとされています。
また、カジュアルな社内連絡や親しい同僚同士の会話では、やや堅苦しく感じられることもあるので、「引き受けます」や「承知しました」など、よりシンプルな表現を選ぶと良いでしょう。
お引き受けいたしますの類語・言い換え表現
「お引き受けいたします」と似た意味を持つ敬語表現や、言い換えが可能なフレーズについてご紹介します。
状況や相手に合わせて、柔軟に使い分けることが大切です。
承知いたしました・承りましたとの違い
「承知いたしました」や「承りました」も、ビジネスでよく使われる敬語表現です。
これらは、相手の依頼や指示、要望を「理解しました」「受け取りました」という意味合いが強く、実際に業務を引き受ける意志を伝える「お引き受けいたします」とは微妙にニュアンスが異なります。
「お引き受けいたします」は、単なる受領ではなく、「責任を持って実行します」という積極的な承諾の姿勢を示す点がポイントです。
そのため、業務の受託やプロジェクトの担当など、具体的な行動を伴う場合に特に適しています。
お受けいたします・お受けしますとの使い分け
「お受けいたします」「お受けします」も似たような意味を持ちますが、「お引き受けいたします」よりもやや一般的・カジュアルな印象があります。
特に、依頼内容が明確でなく、受け入れのニュアンスをソフトにしたい場合には「お受けいたします」を使うと良いでしょう。
一方で、明確に「業務や責任を引き受ける」ことを強調したい場合には「お引き受けいたします」を使うのが適切です。
シーンや相手の立場に応じて、表現を変えるとよりスマートな印象を与えられます。
その他の言い換え例と応用表現
「お引き受けいたします」の他にも、様々な言い換えや応用表現が存在します。
例えば、「かしこまりました」「責任を持って対応いたします」「喜んで承ります」などが挙げられます。
状況によって、「お力になれることがあれば何でもお申し付けください」など、より柔らかく親しみやすい表現も効果的です。
相手との関係性や業務内容に合わせて、最適な敬語を選びましょう。
お引き受けいたしますの注意点とマナー
「お引き受けいたします」を使う際の注意点や、より良い印象を与えるためのマナーについて解説します。
敬語表現を正しく使いこなすことで、信頼関係の構築にも繋がります。
断る場合の適切な対応・表現
全ての依頼を「お引き受けいたします」と受けるわけにはいかない場合もあります。
断る際は、相手への配慮や誠意を込めて、丁寧に理由を伝えることが大切です。
例えば、「誠に申し訳ございませんが、現状の業務状況ではお引き受けいたしかねます」といった形で、お断りの意をやんわりと伝えると良いでしょう。
無理に引き受けてしまうと、後々トラブルになる可能性もあるため、適切な判断と対応が求められます。
過剰敬語や二重敬語に注意
ビジネス敬語は丁寧さが求められますが、「お引き受けさせていただきます」などの二重敬語や、過度な表現は逆効果になる場合があります。
正しい敬語を意識しつつ、簡潔で分かりやすい表現を心掛けましょう。
また、相手の立場や状況に応じて、適度な敬語レベルを選ぶことも大切です。
自然なやりとりを意識し、丁寧さと親しみやすさを両立させるよう心掛けましょう。
誤用を避けるためのポイント
「お引き受けいたします」は、責任を伴う業務や依頼に対して使うのが基本です。
単なる伝言や簡単なお願いごとなど、責任範囲が明確でない場合には、他の表現を選ぶ方が自然です。
また、自分が本当に対応できるかどうかを確認した上で使用することも大切です。
安易に使ってしまうと、後々トラブルになりかねませんので、慎重な判断を心掛けましょう。
まとめ
「お引き受けいたします」は、ビジネスシーンでの信頼構築や円滑なコミュニケーションに欠かせない敬語表現です。
意味や使い方、適切な場面や注意点を押さえておくことで、よりスマートに仕事を進めることができます。
正しい敬語を身につけることで、ビジネスパーソンとしての信頼度がアップします。
ぜひこの記事を参考に、「お引き受けいたします」を自信を持って活用してみてください。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 意味 | 相手の依頼や申し出を丁寧かつ謙譲語で承諾する表現 |
| 使う場面 | ビジネスメール、電話、対面など幅広い場面で使用可能 |
| 類語 | 承知いたしました、承りました、お受けいたします など |
| 注意点 | 二重敬語や過度な丁寧表現、誤用に注意 |