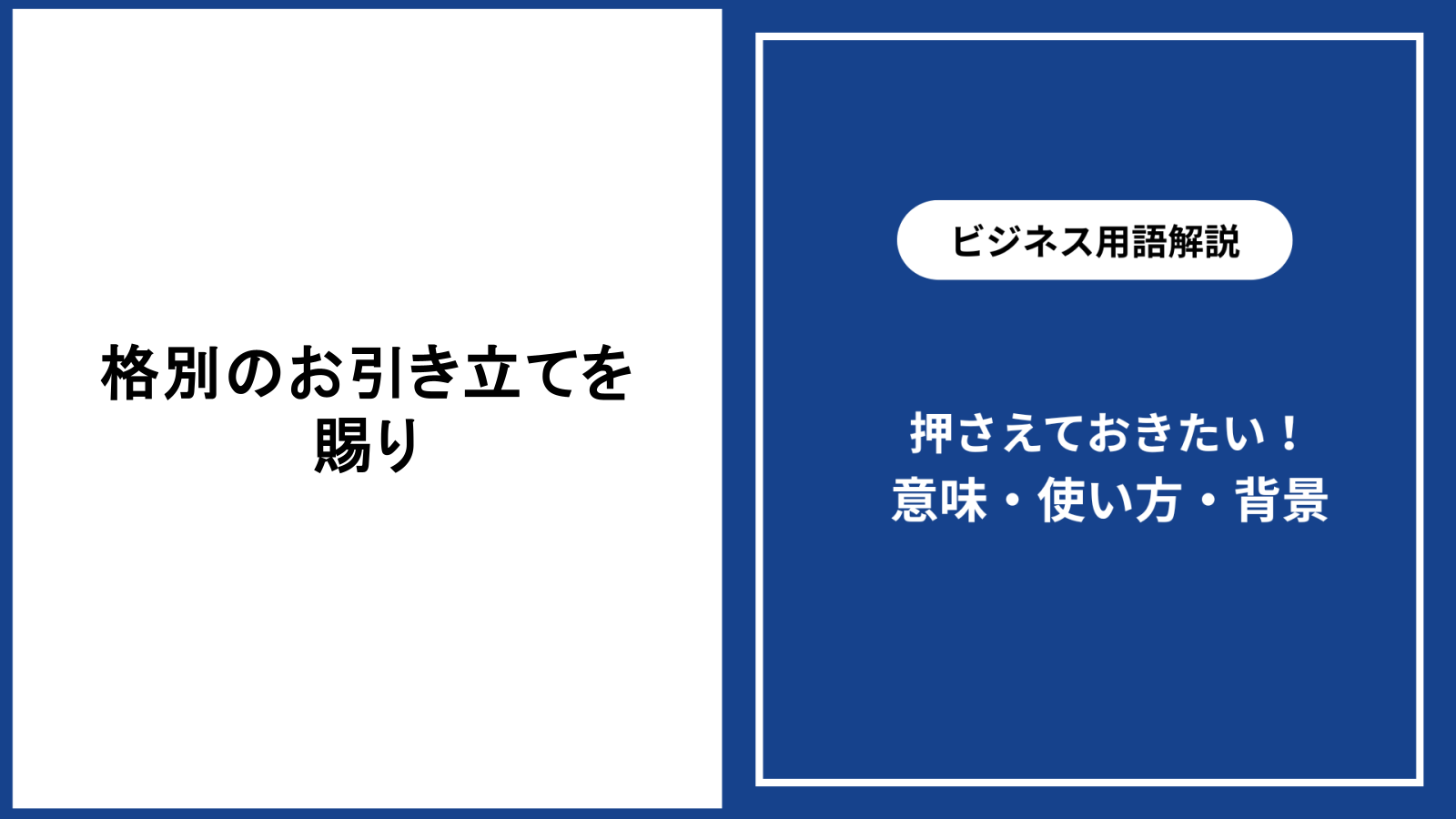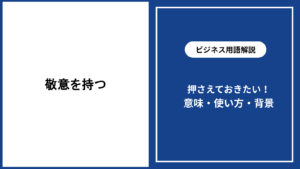ビジネスメールやご挨拶状でよく見かける「格別のお引き立てを賜り」。
しかし、その正確な意味や正しい使い方、類語や注意点までは意外と知られていません。
本記事では、「格別のお引き立てを賜り」の意味や使い方、例文、似た表現との違いまでわかりやすく解説します。
ビジネスシーンで恥をかかないためにも、しっかり理解しておきましょう。
格別のお引き立てを賜りとは?
このフレーズは日本語のビジネスシーンにおいて、感謝や敬意を表すためによく使われます。
どのような意味が込められているのでしょうか。
格別のお引き立てを賜りの意味
「格別のお引き立てを賜り」とは、特別に大切にしてもらっている、または特に厚くご愛顧いただいている、という意味です。
「格別」は「特別」「並外れて」などの意味を持ち、「お引き立て」は「ご贔屓(ひいき)」や「ご支援」を表現します。
「賜り」は「いただき」の謙譲語で、相手から自分が受けている恩恵を丁寧に述べる表現です。
ビジネス文書やメール、年賀状、決算報告など公式な場面で幅広く使われます。
この言葉を使うことで、相手に対し深い感謝と敬意を伝えることができます。
特に、日頃からお世話になっている取引先や顧客に向けて使用すると、関係性を良好に保つ効果が期待できるでしょう。
使われる場面と背景
「格別のお引き立てを賜り」は、主にビジネス文書や公式なメール、挨拶状などで多用されます。
たとえば、年度初めや締めくくりの挨拶状、決算報告書、お礼状、年賀状などに頻出します。
この表現は、相手との信頼関係を築き、今後の取引や関係性の継続を願う気持ちを込めて用いられます。
また、単なる「ありがとうございます」よりも重みがあり、フォーマルな印象を与えます。
構成要素の解説
「格別のお引き立てを賜り」は、3つのパーツから成り立っています。
まず「格別」は、「特に」「非常に」という強調の意味を持ちます。
「お引き立て」は、「ご支援」「ご愛顧」「ご贔屓」といった意味合いです。
最後の「賜り」は、謙譲語で「いただき」に相当します。
このように、最大限の敬意と感謝を示すために、丁寧な言い回しで構成されています。
| 構成要素 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 格別 | 特に、非常に | 格別のご高配 |
| お引き立て | ご愛顧、ご支援 | お引き立てのほど |
| 賜り | いただき(謙譲語) | ご協力を賜り |
ビジネスシーンでの正しい使い方
ビジネスにおいて「格別のお引き立てを賜り」を用いる際には、いくつかのポイントや注意点があります。
具体的な文例や、使うときに気をつけたいポイントを詳しく見ていきましょう。
実際の例文と使い方
例えば、日頃の取引やご支援に感謝を伝える際、次のような文章が使われます。
「平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。」
これは定型的な挨拶文で、取引先やお客様への冒頭挨拶として最適です。
他にも、年末のご挨拶や、事業報告書の冒頭、案内状などでよく使われます。
誤ってカジュアルな相手や、親しい間柄で使うと不自然になるため、必ずフォーマルな場面で使用しましょう。
使い方のポイントと注意点
「格別のお引き立てを賜り」は、目上の方や取引先への感謝の気持ちを表すものです。
同じ社内や目下の相手には使いません。
また、あまりにも多用すると、かえって形式的で心がこもっていない印象を与えてしまう場合があるので注意しましょう。
相手との関係や文書の目的に応じて、最も適切なタイミングや場面で使うことが大切です。
メールや手紙の冒頭で使用し、本文で具体的な感謝の内容や今後の協力依頼を述べると、より丁寧な印象になります。
表現を広げるアレンジ例
シーンによっては、より丁寧にしたり、ややカジュアルにする必要があるかもしれません。
たとえば、「日頃より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます」といった形で、感謝の意を強調することも可能です。
また、「ご高配」や「ご愛顧」と組み合わせて、「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」とするのもよいでしょう。
状況や相手に合わせて表現を選び、真心が伝わる文章を心がけることで、より良いビジネスコミュニケーションが実現します。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 定型挨拶 | 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 |
| 年末年始 | 本年も格別のお引き立てを賜り、心より感謝申し上げます。 |
| 案内・報告 | 格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 |
「格別のお引き立てを賜り」と類語・似た表現
ビジネス文書には似たような表現が多く存在します。
それぞれのニュアンスや使い分けについて知っておくと、さらに表現力がアップします。
よく使われる類語・同義語
「格別のお引き立てを賜り」と意味や用法が近い表現は、以下のようなものがあります。
「ご高配を賜り」、「ご愛顧いただき」、「ご支援を賜り」、「ご厚情を賜り」などです。
これらはどれも、相手から受けている厚意や支援への感謝を表現しています。
ただし、「ご高配」は特に目上の方からの配慮や気遣いに、「ご愛顧」は長期的な支援や利用に対して使うことが多い点に注意しましょう。
類語との正しい使い分け
「格別のお引き立てを賜り」は、取引先や顧客全体への幅広い感謝に適しています。
「ご高配を賜り」は、主に上司やより目上の関係者への配慮や気遣いを強調する言い回し。
「ご愛顧」は、商店やサービス業が顧客に対して使うことが多く、よりカジュアルな印象です。
それぞれの表現の微妙なニュアンスを理解し、状況や相手に合わせて選択することが大切です。
間違えて使うと、相手に違和感や不快感を与える恐れがあるので注意しましょう。
間違えやすい表現・避けるべき使い方
「格別のお引き立てを賜り」は、とても丁寧な表現のため、親しい間柄やカジュアルなやりとりでは不自然に感じられます。
また、同じ文書内で何度も繰り返すとくどくなり、形式的な印象を与えがちです。
「ご贔屓」「ご利用」など、もう少し柔らかい表現に言い換えることで、親近感を持たせることができます。
状況や相手に合わせた表現選びを心がけましょう。
| 表現 | 適した場面 |
|---|---|
| 格別のお引き立てを賜り | 取引先・顧客全般/公式文書 |
| ご高配を賜り | 目上の方・上司への挨拶 |
| ご愛顧いただき | 店舗・サービス業の顧客向け |
| ご支援を賜り | 支援や協力に限定した場合 |
まとめ
「格別のお引き立てを賜り」は、ビジネス文書や公式な挨拶で、相手への深い感謝と敬意を表現する日本語の美しい敬語表現です。
その意味や正しい使い方、類語との違いを理解し、適切なシーンで活用することで、より円滑で信頼されるビジネスコミュニケーションが実現できます。
大切なのは、相手や状況に合わせた表現選びと、真心を込めること。
この記事を参考に、ぜひ日々のビジネスで上手に使いこなしてみてください。