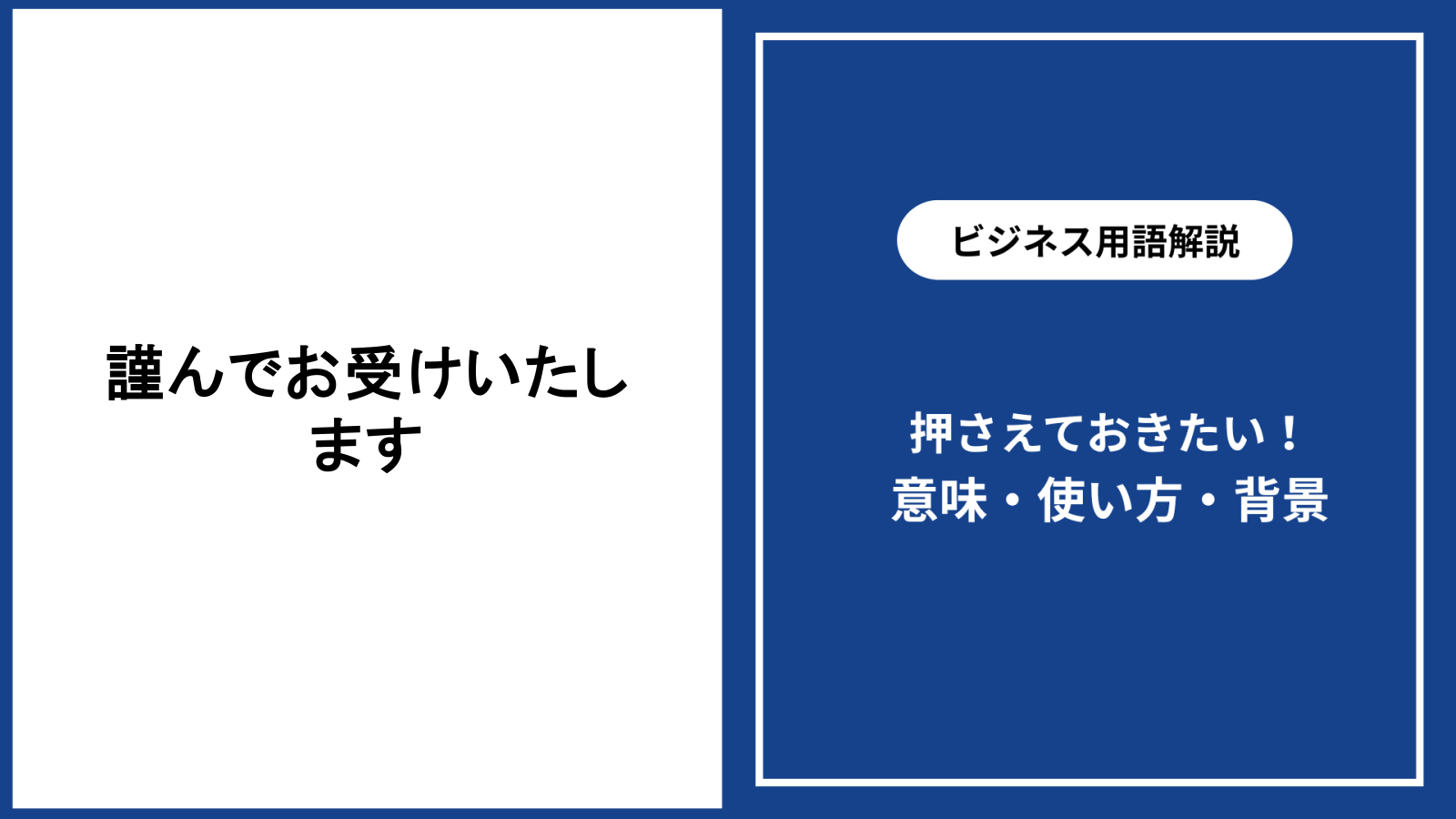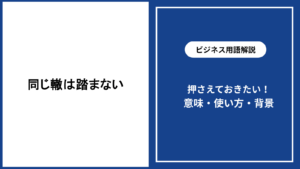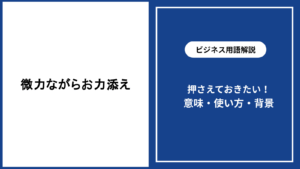「謹んでお受けいたします」は、ビジネスシーンでよく使われる丁寧な敬語の一つです。
大切な依頼や申し出に対して、相手への敬意と感謝を込めて受諾の意思を表す際に用います。
本記事では、この言葉の意味や使い方、類語や注意点、メールや手紙での例文まで分かりやすく解説します。
ビジネスパーソンだけでなく、フォーマルな場面で正しく使いたい方もぜひご覧ください。
謹んでお受けいたしますとは
「謹んでお受けいたします」とは、相手からの依頼や申し出を、慎み深い気持ちで丁重に受け入れることを表現する敬語表現です。
主にビジネスメールや公式な書状、式典などのフォーマルな場面で使用される言葉です。
日常会話で使うことはあまりなく、格式や礼儀を重んじる場面で、その場にふさわしい丁重な表現として用いられます。
「謹んで」は「つつしんで」と読み、慎み深い気持ちや敬意を込めるという意味があります。
「お受けいたします」は、「受ける」の謙譲語であり、相手の申し出や依頼を自分が受け入れることをへりくだって表現しています。
この2つを組み合わせることで、より丁重なニュアンスが加わり、相手への最大限の敬意と感謝を示す表現となります。
言葉の構成と敬語レベル
「謹んでお受けいたします」は、敬語表現の中でも特にレベルが高い部類に入ります。
「謹んで」という語は、謙譲語や丁寧語の最上級にあたり、相手への礼節を最も重視していることを示します。
また、「お受けいたします」も単なる「受けます」よりもはるかに丁重で、ビジネスや儀式的なやりとりにぴったりです。
この言葉を使うことで、相手に対し「あなたの申し出を非常にありがたく、慎み深く承ります」という真摯な気持ちを伝えることができます。
単に「承知しました」や「受け付けます」といった表現よりも、よりフォーマルで礼儀正しい場面で使うのが適切です。
特に目上の方や取引先、公式な案内などで用いられることが多いでしょう。
ビジネスメールでの使い方
ビジネスメールでは、上司や取引先からの依頼、招待、役割の打診などを受けた際に「謹んでお受けいたします」と記載することで、相手への敬意と感謝をしっかり伝えることができます。
たとえば、会議の議長やプロジェクトリーダーの任命、講演依頼、表彰など、重要な役割や依頼に対して返答する際に適しています。
具体的には、メール本文の中で「このたびは◯◯の件、誠にありがとうございます。
謹んでお受けいたします。」といった形で使うことが一般的です。
この表現により、相手に対して真摯な気持ちを伝えることができ、ビジネスマナーとしても高く評価されます。
フォーマルな手紙・挨拶文での使い方
式典や祝賀会、公式な案内状など、フォーマルな手紙や挨拶文でも「謹んでお受けいたします」はよく使われます。
例えば、表彰状の受け取り、役職への就任、慶事への招待など、公的な申し出に対する返事として最適な表現です。
挨拶文の場合、「このたびは栄誉あるご推薦を賜り、謹んでお受けいたします。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。」といった具合に記載すれば、より丁重で好印象を与えられます。
特に格式ある場面や、目上の方とのやりとりでは欠かせない言い回しです。
「謹んでお受けいたします」の類語・言い換え表現
「謹んでお受けいたします」と同じような意味を持つ表現や、似たニュアンスで使える敬語表現もいくつか存在します。
シーンに応じて言い換えることで、相手や場面によりふさわしい表現を選ぶことができます。
主な類語・言い換え例
・「ありがたくお引き受けいたします」
・「光栄に存じます」
・「承知いたしました」
・「お受けいたします」
・「お引き受け申し上げます」
これらの表現は、いずれも依頼や申し出を丁重に受け入れる際に使われますが、「謹んでお受けいたします」は最も格式が高く、重要な役割や正式な場面に向いています。
「ありがたくお引き受けいたします」は、感謝の気持ちがより前面に出る表現です。
「光栄に存じます」は、名誉であることを強調したい場合に適しています。
「承知いたしました」「お受けいたします」は、ややカジュアルな場面や簡単な依頼に使うことが多いでしょう。
使い分けのポイント
重要な役割や公式な依頼、式典など、特に丁重な対応が求められる場面では「謹んでお受けいたします」が最適です。
一方、日常的な業務連絡やちょっとした依頼に対しては、「承知いたしました」「お受けいたします」程度でも十分です。
また、相手が非常に目上であったり、名誉ある話であれば「光栄に存じます」「ありがたくお引き受けいたします」を加えると、より敬意と感謝が伝わります。
場面ごとに適切な敬語表現を選ぶことで、相手への印象や信頼感を高めることができます。
形式や礼儀を重視する場合には、最も丁寧な表現を心がけましょう。
間違いやすい表現との違い
「謹んでお受けいたします」と似ているものの、意味合いや使い方が異なる表現も存在します。
例えば、「ご遠慮いたします」は、やんわりと断る際に使う表現であり、受け入れの意思を示すものではありません。
また、「お受けします」や「承ります」は、ややカジュアルで敬意がやや薄くなります。
格式の高い依頼や公式な場面では、「謹んでお受けいたします」と正確に使い分けることが大切です。
相手との関係や場の雰囲気を考慮し、適切な言葉選びを心がけましょう。
「謹んでお受けいたします」の注意点と使い方のコツ
「謹んでお受けいたします」は非常に丁重な表現ですが、使い方を誤ると不自然な印象や過剰表現と受け取られる場合もあります。
適切な場面や文脈、敬語の重ねすぎに注意しましょう。
使うべき場面と避けるべき場面
「謹んでお受けいたします」は、ビジネスや公的な場面での重要な依頼、役割、招待など、格式や礼儀が求められる時に使うのが適切です。
一方、日常的な業務連絡や、親しい間柄で使うと、かえって堅苦しすぎる印象を与えてしまうことがあります。
例えば、同僚や部下からのちょっとした頼みごとや、社内のカジュアルなやりとりには不要です。
また、自己推薦や自分から申し出る場合には使わないよう注意しましょう。
基本的に、目上の方や公式な場で、相手からの依頼や申し出に対して使うのが正しい使い方です。
敬語の重ねすぎに注意
日本語の敬語は、重ね過ぎると不自然になることがあります。
「謹んでお受けいたします」はすでに十分丁重な表現なので、さらに「~させていただきます」などを加えると、過剰敬語となりやすいです。
例えば、「謹んでお受けさせていただきます」といった表現は、敬語の二重使用で不自然になるため避けましょう。
正しくは「謹んでお受けいたします」のみで十分です。
メールや手紙での例文
以下は、実際のビジネスメールや手紙で使える例文です。
シーン別に覚えておくと便利です。
【メール例文】
拝啓 このたびは◯◯のご依頼を賜り、誠にありがとうございます。
謹んでお受けいたしますとともに、微力ながら尽力させていただく所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
【手紙例文】
このたびは栄誉あるご推薦を賜り、誠にありがとうございます。
謹んでお受けいたしますとともに、今後も一層の努力を重ねてまいります。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
まとめ
「謹んでお受けいたします」は、相手への最大限の敬意と感謝をもって、慎み深く申し出や依頼を受け入れる際に使う、格式の高い敬語表現です。
ビジネスや公的な場面、公式な手紙やメールなどで、重要な依頼や役割を引き受ける際に最適です。
使い方を誤らないためには、場面や相手との関係、敬語の重ねすぎに注意しましょう。
類語や例文も参考に、適切な場面で上手に使いこなしてください。
本記事を参考に、より一層丁寧で好印象なコミュニケーションを目指しましょう。
| 表現 | 主な使用場面 | ポイント |
|---|---|---|
| 謹んでお受けいたします | ビジネス・公式・式典など | 最上級の敬意・感謝を示す |
| ありがたくお引き受けいたします | 名誉ある依頼や招待 | 感謝の気持ちを強調 |
| 光栄に存じます | 賞賛・推薦・役職就任 | 名誉であることを表現 |
| 承知いたしました | 日常的な業務連絡 | カジュアルな受諾 |
| お受けいたします | 一般的な依頼 | 丁寧だがカジュアル |