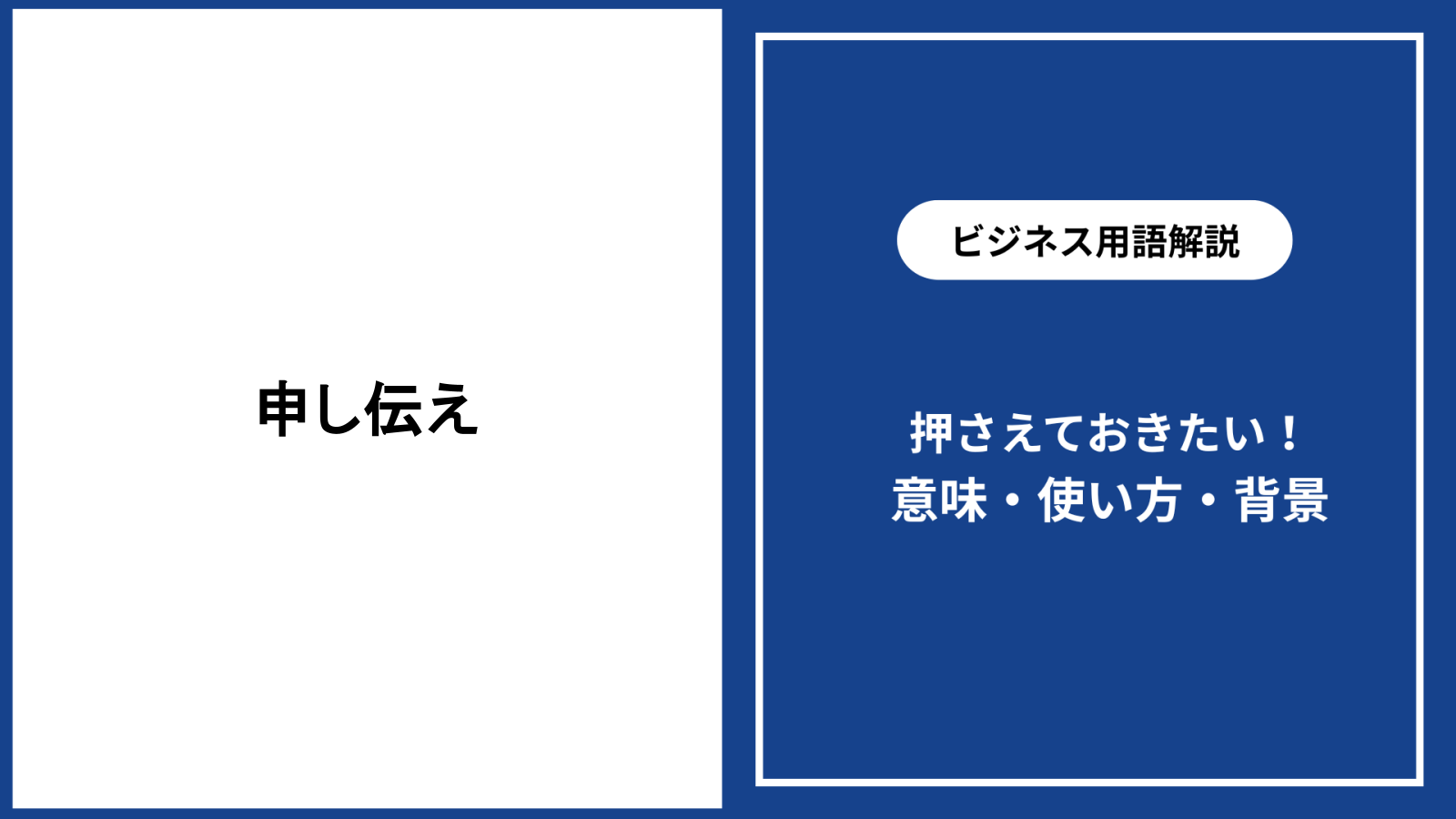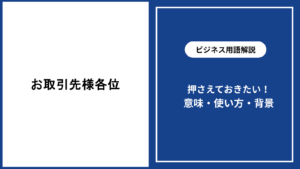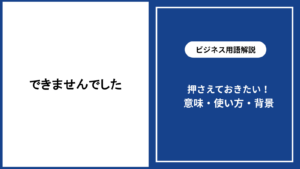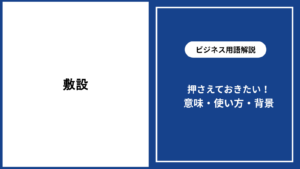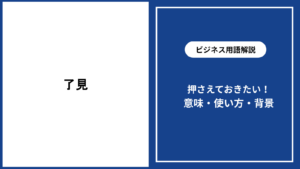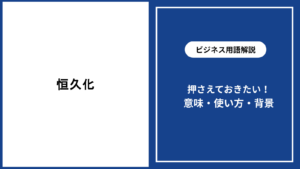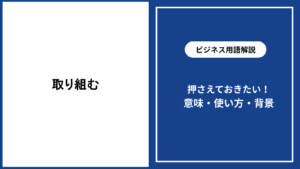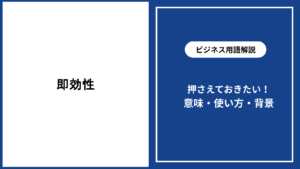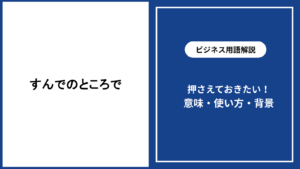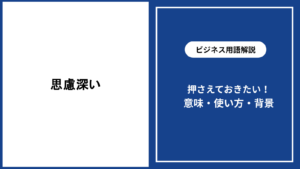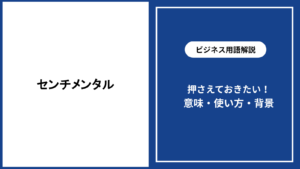ビジネスシーンや日常会話で見聞きする「申し伝え」。
意味や正しい使い方、似た言葉との違いを知らないと、思わぬ誤解を招くことも。
この記事では、「申し伝え」の基本から、気をつけたいビジネスマナーや例文まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。
申し伝えとは?意味と特徴をやさしく解説
「申し伝え」は、相手に何かを伝達する際に用いる、丁寧な日本語表現です。
主にビジネスやフォーマルな場面で使われ、自分が直接伝えるのではなく、第三者を通して伝言する意味を持ちます。
この言葉のニュアンスや由来、日常とビジネスでの使い方の違いを知ることで、あなたのコミュニケーション力がぐっとアップします。
「申し伝え」は、「伝える」という動作に「申し上げる」(謙譲語)を加え、より丁寧さを強調した表現です。
自分が伝言役となる際や、相手の伝言を預かる際など、敬意を表す必要のある場面で頻繁に登場します。
申し伝えの基本的な意味とニュアンス
「申し伝え」は、自分が伝える内容を、相手や第三者に丁寧に伝える言葉です。
例えば、「上司に申し伝えます」と言えば、「上司にあなたの話をきちんと伝えます」という意味になります。
ここで大切なのは、「申し伝え」は自分が直接伝える場合ではなく、伝言や連絡、報告を代行する時に使う点です。
この丁寧な言い回しによって、相手への敬意を示しながら、伝達役としての立場を明確にできます。
また、「申し伝え」はビジネス上の電話応対やメールで特によく使われ、フォーマルで礼儀正しい印象を与えます。
状況によっては、「伝えておきます」よりもワンランク上の丁寧さを求められる場面で選ばれることが多いです。
申し伝えの語源と歴史的背景
「申し伝え」は、日本語の敬語表現における「申し上げる」と、動詞「伝える」が組み合わさった形です。
「申す」は「言う」の謙譲語、「伝える」は情報や意見を他者へ届ける動作を指します。
この2つが合わさることで、「自分がへりくだって、相手や第三者に内容を丁寧に伝える」意味が生まれました。
歴史的には、江戸時代から公的文書や儀礼的な場面で「申し伝え」が使われてきました。
現代でも、ビジネスや公的なやり取りでその伝統が受け継がれ、相手を立てる日本人らしい配慮が表現されています。
申し伝えが使われる主なシーン
「申し伝え」は、ビジネスの電話応対、メール、面談、会議で多用されます。
特に、自分がその場で伝えきれない内容を、他の誰かに伝達する場合に重宝されます。
例えば、「担当者が不在のため、戻りましたら申し伝えます」といったフレーズは定番です。
また、社内外のやり取りで相手の立場や年齢、関係性を配慮しながら使うことで、礼儀正しく丁寧な印象を与えることができます。
ビジネスマナーの一環として、正しい使い方を身につけておくと便利です。
申し伝えの正しい使い方と例文集
ここでは「申し伝え」の使い方や、よく使われる例文を紹介します。
ビジネス敬語としてのポイントや、間違えやすい使い方にも注意しましょう。
ビジネスメール・会話での申し伝えの例文とコツ
ビジネスメールや会話で「申し伝え」を使うときは、相手に対する丁寧な配慮を意識しましょう。
定番の例文としては、
「ご用件、担当者に申し伝えます」
「ご要望につきまして、上司に申し伝えます」
「お言葉、必ず申し伝えます」
などがあります。
コツは、「申し伝えます」をクッション言葉や感謝のフレーズと組み合わせることです。
例えば、「貴重なご意見を、必ず上司に申し伝えます。ありがとうございました」とすると、より印象が良くなります。
また、「申し伝えます」は未来の行動を表すため、「今後伝えます」というニュアンスになります。
申し伝えと「伝えておきます」「申し上げます」の違い
「申し伝え」は、第三者を通して伝言を届ける際の丁寧語です。
一方、「伝えておきます」はややカジュアルで、敬語度が低め。
「申し上げます」は、直接相手に伝える場合の謙譲語で、伝言役には向きません。
ビジネスでは、役割や状況に応じて使い分けることが大切です。
相手や場面に合った敬語を選ぶことで、信頼感や好印象につながります。
間違えやすいNG例と注意点
「申し伝え」を間違って使うと、逆に失礼になることもあります。
例えば、「私が申し伝えます」と自分の話を直接伝える場合は不適切です。
また、目上の人に対して「申し伝えてください」と依頼するのもNG。
自分より立場が上の人に「伝言役」を頼む表現は避けましょう。
さらに、「申し伝えました」と過去形で使う場合は、確実に伝えた事実がある時に限定しましょう。
まだ伝えていないのに「申し伝えました」と言うと、信用を失う原因になります。
申し伝えを使う際のビジネスマナー
ビジネスシーンで「申し伝え」を使うときは、敬語の正しい使い方が重要です。
相手や状況に配慮した言葉選びで、より良いコミュニケーションを目指しましょう。
敬語の組み合わせと正しいフレーズ例
「申し伝え」は単体でも丁寧ですが、他の敬語表現と合わせることで、さらに丁寧な印象になります。
例えば、
「かしこまりました。ご用件、必ず申し伝えます」
「恐れ入りますが、上司に申し伝えます」
などが挙げられます。
クッション言葉(「恐れ入りますが」「承知いたしました」など)を前につけることで、より円滑なやりとりが可能です。
また、相手に安心感を与えるために「必ず」や「丁寧に」を添えることも効果的です。
電話応対や来客対応での申し伝えのポイント
電話や来客対応で「申し伝え」を使う際は、相手の立場や要望を正確に把握することが大切です。
例えば、「担当者が不在ですので、戻り次第、申し伝えます」といった表現で、迅速かつ丁寧に伝言を預かることができます。
また、伝達内容の復唱や確認を行うことで、情報の行き違いを防げます。
「ご用件を復唱いたします。○○ですね。必ず申し伝えます」と丁寧な対応を心がけましょう。
「申し伝えました」など過去形の使い方
「申し伝えました」は、既に伝言や内容を相手に届けたことを報告する表現です。
報告や進捗連絡、アフターフォローの場面でよく使われます。
ただし、事実と異なる場合は絶対に使用しないことが大前提です。
「本日、上司に申し伝えました」「ご要望、担当者に申し伝えました」といった表現で、進行状況を明確に伝えられます。
申し伝えに関連する類語・言い換え表現
「申し伝え」以外にも、似た意味の表現がいくつか存在します。
状況や相手に応じて、適切な言い回しを選びましょう。
「伝言・お伝えします」との使い分け
「伝言」「お伝えします」は、「申し伝え」よりややカジュアルまたは一般的な表現です。
「伝言」は口頭やメモ、メールなど幅広く使われ、フォーマルさがやや控えめです。
「お伝えします」は、直接伝える場合や社内のやり取りでよく使われます。
「申し伝え」は、より丁寧で格式の高い場面に適しています。
取引先やお客様など、目上や外部の方に対しては「申し伝え」を選ぶのが無難です。
「申し上げる」「承る」との違い
「申し上げる」は、自分が直接相手に伝える場合の謙譲語です。
たとえば、「ご意見を申し上げます」といった使い方が一般的です。
一方、「承る」は「聞く・受ける」の謙譲語で、伝言を預かる・承知する意味で用います。
「申し伝え」は、伝言や連絡を預かって、第三者へ届ける際の丁寧語という点が大きな違いです。
状況に応じて、使い分けを意識しましょう。
場面別・申し伝えの適切な言い換え
状況によっては「申し伝え」以外の表現が適切な場合もあります。
例えば、
・社内の同僚へは「伝えておきます」
・目上の上司へは「お伝えいたします」
・お客様や取引先へは「申し伝えます」
など、相手との関係性やTPOを考慮して選びましょう。
「申し伝え」は丁寧すぎると感じる場合や、カジュアルな場面では他の表現を使うのもポイントです。
まとめ|申し伝えの意味と使い方を正しく理解しよう
「申し伝え」は、伝言や情報を第三者に丁寧に伝える際の敬語表現です。
ビジネスやフォーマルな場面で使うことで、相手への敬意やマナーをしっかり示すことができます。
使い方を誤ると失礼になることもあるため、意味や例文、類語との違いをしっかり押さえておきましょう。
状況や相手に合わせて、適切な敬語表現を選ぶことで、信頼と円滑なコミュニケーションを築けます。
「申し伝え」をマスターして、ビジネスシーンでも好印象を与えましょう。
| 表現 | 意味・使い方 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 申し伝え | 第三者を通じて内容を丁寧に伝える | ビジネス、フォーマルな伝言・報告 |
| 伝えておきます | ややカジュアルな伝言表現 | 社内、同僚、フランクな場面 |
| 申し上げます | 直接相手に伝える謙譲語 | 意見表明、フォーマルな自己表現 |
| 承る | 要件などを丁寧に受ける | 注文受付、要望・依頼の承知 |