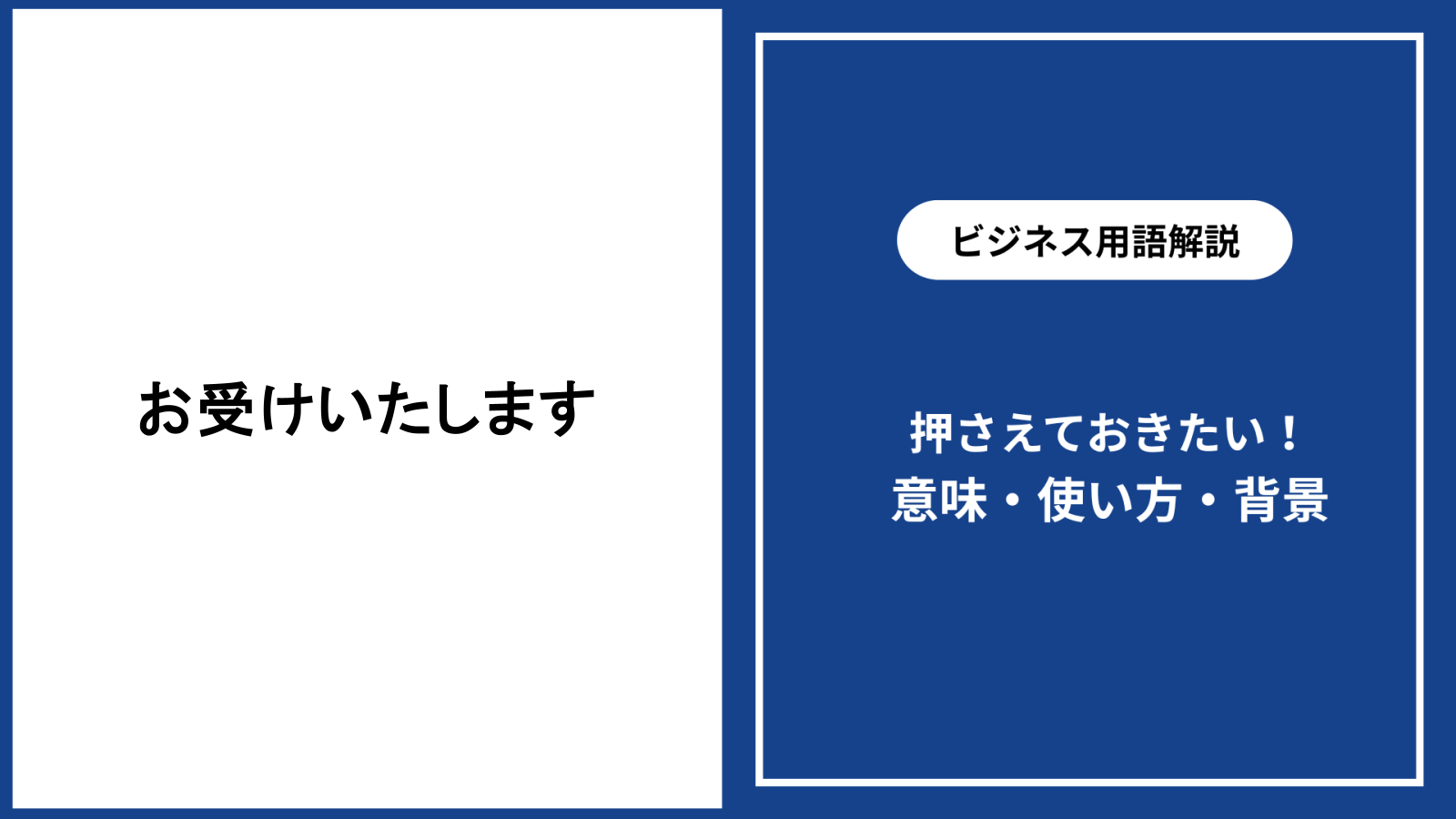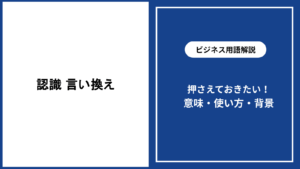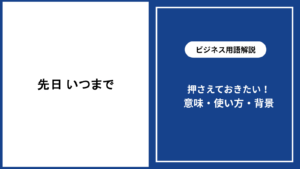「お受けいたします」はビジネスシーンや日常会話でよく使われる表現です。
依頼や申し出を快く引き受けるとき、相手に丁寧な印象を与えるための敬語表現として広く活用されています。
この記事では「お受けいたします」の意味や使い方、メール例文、似た表現との違いまで、わかりやすく詳しく解説します。
社会人の方や就活生、そしてビジネスメールを書く機会の多い方はぜひ最後までご覧ください。
正しい使い方を知ることで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。
お受けいたしますの基礎知識と正しい意味
「お受けいたします」は、依頼や申し出、仕事などを謹んで引き受けるという意味を持つ敬語表現です。
主にビジネスメールや電話対応、接客の場面で使われています。
この表現は、単なる「受けます」や「引き受けます」よりも丁寧さや謙虚さを強調するため、相手に敬意を伝えたい場合に適しています。
「お受けいたします」の言葉の成り立ち
「お受けいたします」は「受ける」に尊敬語の接頭辞「お」と、謙譲語「いたす」が組み合わさった敬語です。
「いたします」は「する」の謙譲語で、話し手自身の動作をへりくだって表現し、相手への敬意を表します。
そのため、「お受けいたします」は自分が引き受けることを控えめな表現で相手に伝えるフレーズとなっています。
ビジネスにおいては、依頼やお願い事に対して前向きに応じる意志を示す際に使うと、相手に丁寧な印象を与えられます。
ビジネスメールや電話での使い方
「お受けいたします」は、ビジネスメールや電話対応などさまざまなシーンで活躍します。
例えば、会議の出席依頼や資料作成の依頼、商談の申し込みなどに対し、「はい、承知しました」よりも丁寧に応じたい場合、「お受けいたします」と返答します。
例文としては、「ご依頼の件、お受けいたします。」や「ご相談内容について、お受けいたしますので、よろしくお願いいたします。」などが挙げられます。
相手の申し出に対して前向きな姿勢を示しつつ、丁寧な印象を与えることができます。
「お受けいたします」が使われる具体的なシーン
「お受けいたします」は、以下のようなビジネスシーンでよく使われます。
・取引先からの業務依頼
・社内でのタスク割り当て
・顧客からの問い合わせや要望への対応
・イベントや会議への出席依頼
どの場面でも「お受けいたします」と返すことで、相手への敬意を示し、信頼感を与えることができます。
そのため、社会人として身につけておきたい表現です。
お受けいたしますの例文とメール文面
ここでは、「お受けいたします」を使ったビジネスメールの例文や、電話・チャットでの使い方を紹介します。
適切な例文を参考に、正しい使い方を身につけていきましょう。
ビジネスメールでの例文
ビジネスメールでは、相手からの依頼やお願いごとに対して「お受けいたします」と丁寧に表現することで、信頼感や誠意を示すことができます。
例えば、次のようなメール文面が考えられます。
例文:
「〇〇の件、お受けいたします。詳細につきましては改めてご連絡いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。」
このように「お受けいたします」を文中に盛り込むことで、相手に敬意を払った肯定の返答ができます。
電話や対面での使い方
電話や対面でも「お受けいたします」はよく使われます。
依頼や質問に対して、「はい、お受けいたします」や「ご依頼、お受けいたしますので、よろしくお願いいたします」などと返答すると、スマートで丁寧な印象を与えることができます。
特にビジネスの現場では、クッション言葉や前置きを加え「恐れ入りますが」「かしこまりました」などと組み合わせて使うことで、より洗練された対応が可能となります。
チャット・社内連絡での使用例
最近では社内チャットやLINE WORKS、Slackなどのビジネスチャットでも「お受けいたします」はよく活用されます。
カジュアルなやり取りでも丁寧さを保ちたい場合、「承知しました」「了解しました」よりも敬意を強調したいときに選ばれる表現です。
例えば、「本日の会議の議事録作成について、お受けいたします。」といった形で使えば、相手への配慮や丁寧さが伝わります。
「お受けいたします」と類似表現・言い換え
「お受けいたします」には、似た意味を持つ表現や言い換えがいくつか存在します。
状況や相手との関係性に応じて、適切な言葉を選ぶことが大切です。
「承知いたしました」との違い
「承知いたしました」は「内容を理解し、受け入れた」ことを示す表現です。
一方、「お受けいたします」は「依頼や申し出を実際に引き受ける」ことを意味します。
つまり、「承知いたしました」は情報を受け取り、理解したことを表現し、「お受けいたします」は実際に行動する意思を強調する点が異なります。
「お引き受けいたします」との使い分け
「お引き受けいたします」も「お受けいたします」とほぼ同じ意味を持ちますが、やや重々しく、責任の重さや正式さを強調したいときに使われる傾向があります。
例えば、重要なプロジェクトや責任ある業務に対しては「お引き受けいたします」とするとより適切です。
日常的な業務や軽めの依頼には「お受けいたします」を使うとバランスが良いでしょう。
状況や業務の重みで使い分けるのがポイントです。
その他の言い換え表現
「お受けいたします」以外にも、以下のような表現がよく使われます。
・かしこまりました
・お引き受けします
・お引き受けいたします
・承ります
どれも丁寧な敬語ですが、「お受けいたします」が最も一般的でバランスが良い表現です。
相手や場面に合わせて、自然に使い分けましょう。
お受けいたしますの注意点・正しい使い方
「お受けいたします」は便利な表現ですが、注意点もあります。
正しい使い方を理解しておくことで、より信頼されるビジネスパーソンを目指しましょう。
使いすぎや不適切な場面に注意
「お受けいたします」は丁寧な表現ですが、すべての依頼や申し出に使うと形式的に感じられたり、機械的な印象を与えることもあります。
また、自分で決裁できない内容や、責任を持てない案件に対して不用意に使うと、トラブルの原因になる可能性もあるため注意が必要です。
必ず自分の権限や状況を確認した上で使いましょう。
敬語の重ねがけや二重敬語に注意
「お受けいたします」はすでに敬語表現です。
「お受けさせていただきます」などのように、敬語を重ねてしまうと不自然な表現になってしまうので注意しましょう。
シンプルに「お受けいたします」と伝えることで、すっきりとした印象になります。
断る際は別の表現も活用
どうしても依頼を引き受けられない場合には、「申し訳ありませんが」「あいにくですが」など、やんわりと断る表現を使うことが大切です。
単に「お受けいたしかねます」だけでなく、理由や代替案を添えると、より丁寧な印象になります。
断る場合も相手への配慮を忘れずに表現しましょう。
まとめ|お受けいたしますの正しい使い方を身につけよう
「お受けいたします」はビジネスシーンで非常に重宝される敬語表現です。
正しい意味や使い方、例文、類似表現との違い、注意点までしっかり理解し、状況に応じて使い分けることで、より信頼されるコミュニケーションが可能となります。
丁寧な言葉選びで、相手に敬意を伝えつつ、円滑なやりとりを心がけましょう。
今後のビジネスメールや会話で「お受けいたします」をぜひ活用してみてください。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 意味 | 依頼や申し出を丁寧に引き受ける敬語 |
| 使い方 | ビジネスメール・電話・チャットなどで活用 |
| 注意点 | 使いすぎや二重敬語に注意、自分の権限を確認 |
| 類似表現 | 承知いたしました、お引き受けいたします、かしこまりました、など |