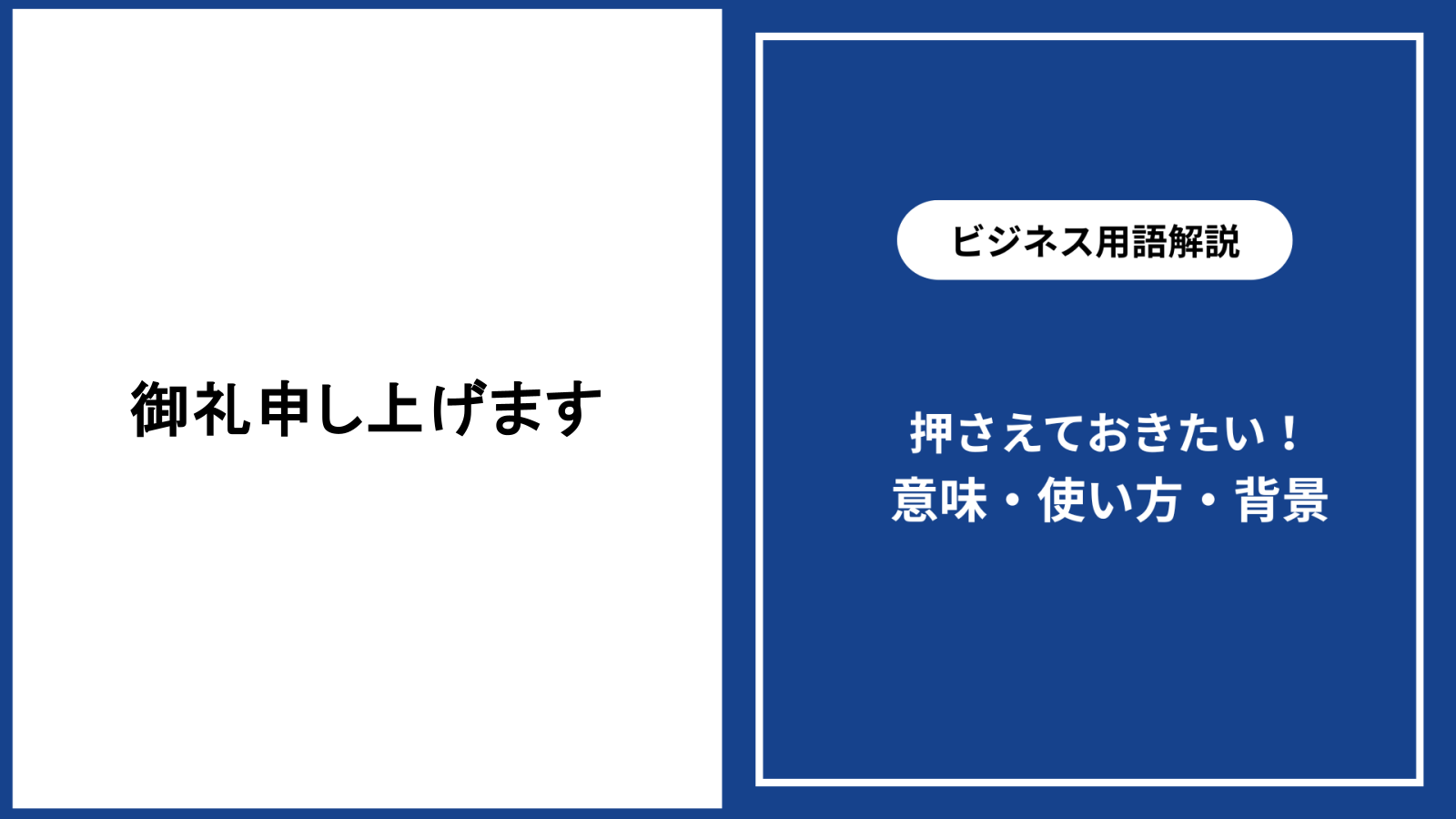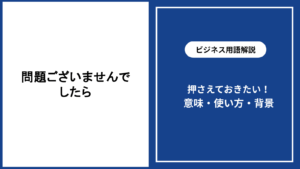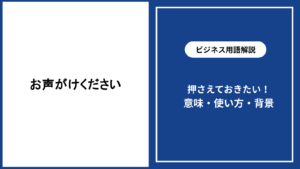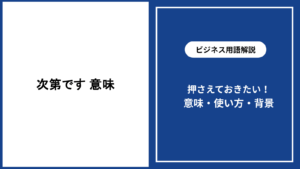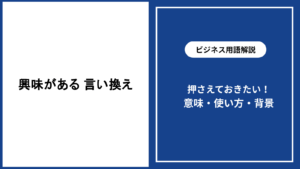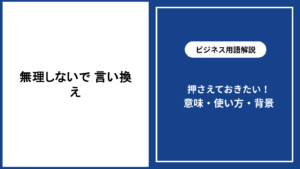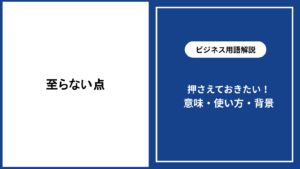「御礼申し上げます」は、ビジネスシーンやフォーマルな場面でよく使われる丁寧な表現です。
普段のやり取りから、取引先や目上の人とのメール、手紙まで、さまざまなシチュエーションで使われています。
この記事では、「御礼申し上げます」の正しい意味や使い方、使う際の注意点などを詳しく解説します。
使用例や似た言葉との違いも併せてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
御礼申し上げますとは?意味と使い方の基本
「御礼申し上げます」は、日本語のビジネス表現の中でも特に丁寧な感謝の言葉です。
相手に対する敬意と感謝の気持ちを、最大限に伝えるために使われます。
日常の会話ではあまり聞かれませんが、ビジネスメールや挨拶状、フォーマルな手紙などでは頻繁に使われます。
この表現には、「心から感謝しております」「ありがたく思います」という意味が込められています。
「御礼」は「お礼」をさらに丁寧にした表現で、「申し上げます」は「言う」「述べる」の謙譲語です。
そのため、自分が相手に対して特に丁重に感謝を伝えたい場合に用います。
「御礼申し上げます」を使う場面と適切なタイミング
「御礼申し上げます」は、ビジネスメールや書状で最もよく使われます。
たとえば、お世話になった相手に対するお礼、贈り物や協力・支援への感謝、取引先の対応への謝意など、幅広いシーンで用いられます。
また、イベントや式典の挨拶文、報告書の冒頭や締めくくりでもよく見かけます。
この表現は、特に目上の人や取引先など、敬意を示すべき相手に向けて使うのが一般的です。
カジュアルな会話や親しい同僚、友人とのやり取りではやや堅苦しく感じられるため、フォーマルなシーンに限定して使うのが適切です。
「御礼申し上げます」の具体的な例文
ここでは、実際のビジネスメールや手紙でよく使われる「御礼申し上げます」の例文をご紹介します。
・この度は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
・平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
・ご多忙中にもかかわらず、早速のご対応をいただき、誠に御礼申し上げます。
・貴重なお時間を割いていただき、深く御礼申し上げます。
これらの例文は、フォーマルなビジネス文書やメールの冒頭・結び・謝辞などで幅広く使うことができます。
また、「御礼申し上げます」は単体で使うだけでなく、前後に具体的な感謝の内容を添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。
「御礼申し上げます」と「ありがとうございます」の違い
「御礼申し上げます」と「ありがとうございます」は、どちらも感謝を表す言葉ですが、その丁寧さや使い方に違いがあります。
「ありがとうございます」は比較的カジュアルで、日常会話からビジネスまで幅広い場面で使えますが、「御礼申し上げます」はより格式高く、改まった場や目上の人に向けて使う表現です。
たとえば、取引先やお客様への正式な文書、挨拶状や礼状、年賀状などでは「御礼申し上げます」が適しています。
一方、社内の同僚や親しい相手には「ありがとうございます」や「お礼申し上げます」など、少し柔らかい表現を選ぶことが多いです。
ビジネスメールや書面での「御礼申し上げます」使い方ポイント
ビジネスシーンで「御礼申し上げます」を使う際には、いくつかのポイントに注意が必要です。
使い方を誤ると、相手に違和感を与えることもあるため、正しいマナーを身につけておきましょう。
「御礼申し上げます」の前後に添えるフレーズ
「御礼申し上げます」は、単独で使うよりも前後に具体的な内容や挨拶文を添えることで、より丁寧で温かみのある文章になります。
たとえば、「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」「ご多忙中にもかかわらず、ご対応いただき、深く御礼申し上げます」など、感謝の理由や状況を明記するのがポイントです。
また、締めくくりや追伸として用いる場合は、「今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心より御礼申し上げます」のように、今後への期待やお願いを添えても良いでしょう。
「御礼申し上げます」は二重敬語ではない?
「御礼申し上げます」という表現は、一見すると「御礼」と「申し上げます」で二重の敬語表現になっているように感じる方もいるかもしれません。
しかし、「御礼」は名詞の丁寧語、「申し上げます」は動詞の謙譲語であり、二重敬語にはあたりません。
そのため、ビジネス文書や公式な場面でも、安心して使える表現です。
ただし、「御礼を申し上げさせていただきます」のように、さらに重ねてしまうと不自然になるので注意しましょう。
書き出し・締めくくりでの活用方法
ビジネスメールや挨拶状では、「御礼申し上げます」を書き出しや締めくくりに使うことがよくあります。
書き出しでは、「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」のように、季節の挨拶や相手の健康を気遣う言葉と組み合わせて使うのがおすすめです。
締めくくりでは、「今後とも変わらぬお付き合いを賜りますよう、心より御礼申し上げます。」や「ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく御礼申し上げます。」のように、今後の関係性を意識した表現を用いると好印象となります。
「御礼申し上げます」と類似表現の違い・使い分け
「御礼申し上げます」以外にも、ビジネスやフォーマルな場で使える感謝の表現はいくつかあります。
それぞれの言葉のニュアンスや使い分けについて詳しく見ていきましょう。
「お礼申し上げます」との違い
「御礼申し上げます」と「お礼申し上げます」は、どちらも丁寧な感謝の表現です。
しかし、「御礼」のほうがより格式高く、公的な手紙や公式文書で使われる傾向があります。
「お礼申し上げます」はやや柔らかい印象となり、社内文書や少しカジュアルな場面でも使いやすいです。
どちらを使うかは、相手との関係性や場面のフォーマル度合いを考慮して選ぶと良いでしょう。
「感謝申し上げます」との違い
「感謝申し上げます」もまた非常に丁寧な表現ですが、「感謝」の方がより抽象的で心情を強調するニュアンスがあります。
「御礼申し上げます」は、具体的な行為や支援へのお礼を伝える時に使うことが多いです。
例えば、「多大なるご協力に対し、感謝申し上げます」のように、心からの深い感謝を伝えたい場合には「感謝申し上げます」が適しています。
「ありがとうございます」等のカジュアルな表現との違い
「ありがとうございます」は、ビジネスから日常まで幅広く使える万能な感謝表現です。
しかし、「御礼申し上げます」に比べると、格式や丁寧さが一段下がるため、目上の人や大切な相手にはやや物足りなく感じられる場合があります。
場面に応じて、より丁重な表現を選ぶことが、ビジネスパーソンとしての品格を高めるポイントです。
また、社交辞令的な場面や公式な挨拶・礼状には「御礼申し上げます」を選ぶことで、相手に対する敬意をよりしっかりと伝えることができます。
まとめ|「御礼申し上げます」で伝える感謝の心
「御礼申し上げます」は、ビジネスやフォーマルなシーンで感謝を伝える際に欠かせない丁寧な表現です。
使う場面や相手に応じて、適切な言い回しや前後のフレーズを工夫することで、より心のこもったメッセージとなります。
相手への敬意や感謝の気持ちをしっかり伝えたい時、ぜひ「御礼申し上げます」を活用してみてください。
適切な言葉選びで、円滑な人間関係や信頼関係の構築にもつながります。
場面や相手に合わせて正しく使い分けることが、社会人のマナーとしてとても重要です。
ぜひこの記事を参考に、より素敵なビジネスコミュニケーションを実践してください。
| 表現 | 丁寧さ | 主な使用場面 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 御礼申し上げます | 非常に丁寧 | ビジネス、公式文書、目上の人への手紙 | 最高クラスの敬意と感謝 |
| お礼申し上げます | 丁寧 | 社内文書、ややカジュアルな場面 | やや柔らかい印象 |
| 感謝申し上げます | 非常に丁寧 | 強い感謝や心情を伝えるとき | 心からの感謝を強調 |
| ありがとうございます | 一般的 | 日常会話、幅広い場面 | 万能な感謝表現 |