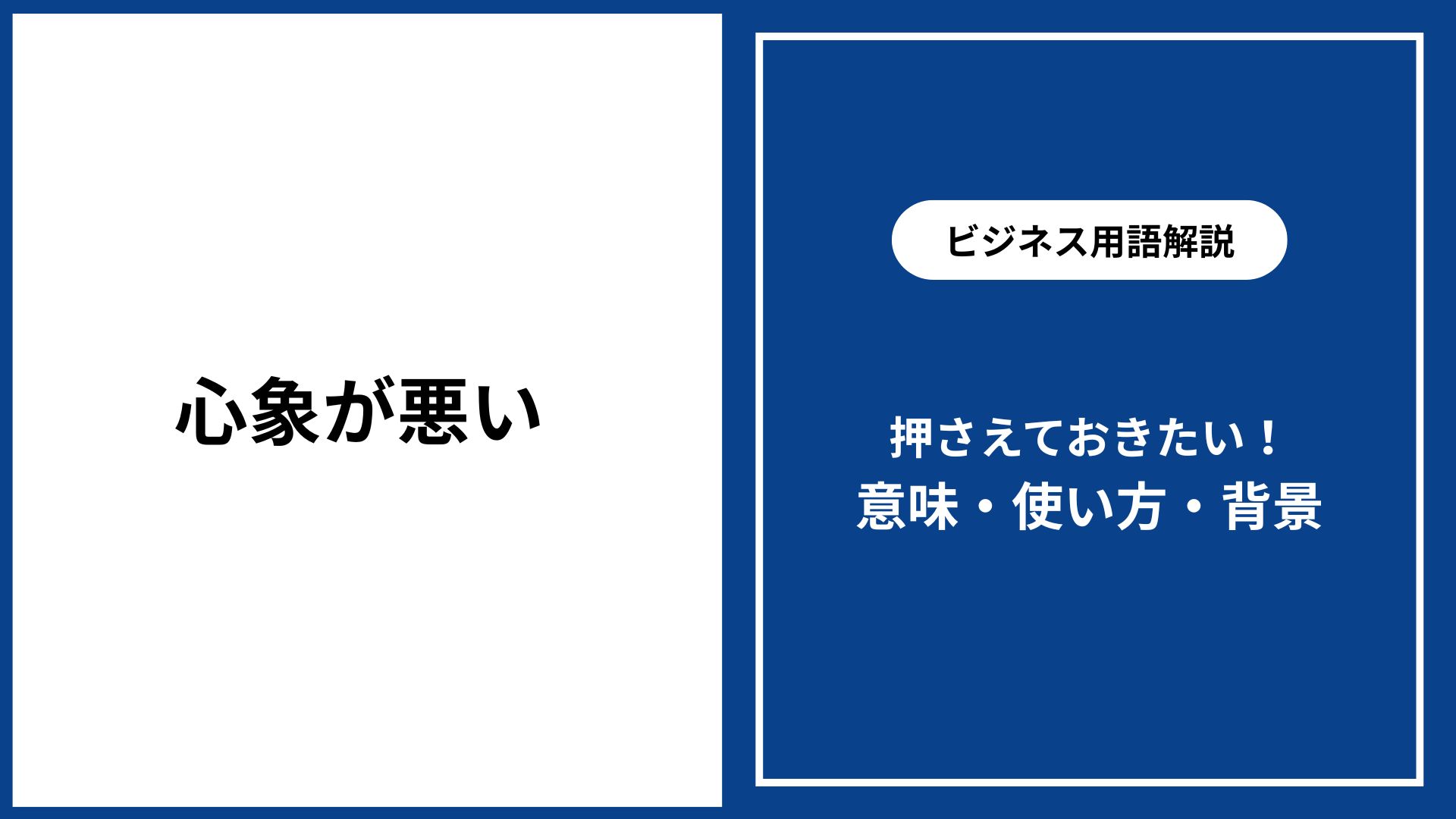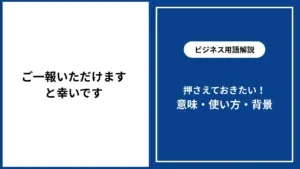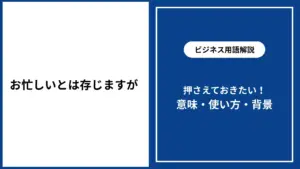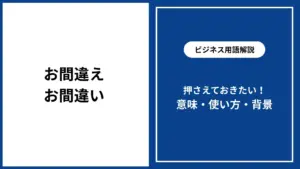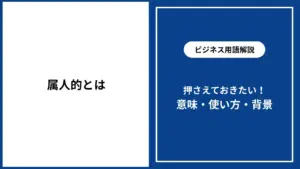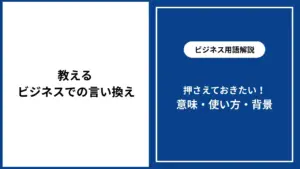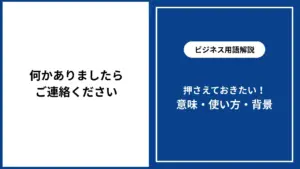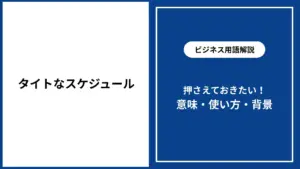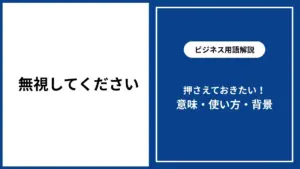「心象が悪い」という言葉は、日常会話だけでなくビジネスシーンでも使われることのある表現です。
相手や出来事について「良い印象を持たない」「不快に感じる」といった意味で用いられます。
この記事では、「心象が悪い」の正しい意味や使い方、ビジネスでの言い換え表現や注意点について詳しく解説します。
「心象が悪い」とは?意味と特徴
「心象(しんしょう)」とは、心の中に浮かんだイメージや印象、感じ方のことを指します。
したがって「心象が悪い」とは、ある人・物事・出来事に対して、心の中で持つ印象やイメージが良くない状態を表します。
例えば、「今回の対応は心象が悪い」「発言が心象を悪くする」などの使い方がされます。
「悪い印象を与える」「不快に思う」「不信感につながる」といったニュアンスが含まれています。
「印象」との違いは?
「心象」と「印象」は似た意味を持ちますが、「印象」は実際に受けたイメージ、「心象」はより主観的で心の奥の感情に近い表現です。
「印象が悪い」よりも「心象が悪い」のほうが、感情的・心理的な反発や拒否感を強く示す場合があります。
「心象が悪い」の主な使い方
・取引先やお客様の前で失礼な態度をとると、心象が悪くなってしまう。
・メールの返信が遅いと、相手に心象が悪い印象を与える場合がある。
・不用意な発言は、社内の心象を悪くするので注意が必要だ。
このように、態度や行動が相手の“心の印象”に悪影響を与える時に使います。
ビジネスで使える「心象が悪い」の言い換え表現
「心象が悪い」はやや主観的なニュアンスを含むため、ビジネスシーンでは少し言い換えて使うのが適切な場合があります。
ここでは丁寧で角の立たない言い換え例や、メール・会話での使い方を紹介します。
主な言い換え表現
- 印象が良くない
- 好印象を持たれにくい
- あまり良いイメージを与えない
- マイナスな印象を持たれる
- ご不快な思いをさせる
- 誤解を招く恐れがある
- ご信頼を損なう可能性がある
これらの表現を使うことで、より柔らかく、ビジネス上の指摘や注意が伝えやすくなります。
ビジネスメール・会話での例文
例1:
「このご案内文は、お客様にあまり良い印象を与えない可能性があります。」
例2:
「不用意な言動は、相手にご不快な思いをさせる恐れがございますので、ご留意ください。」
例3:
「対応が遅れると、ご信頼を損なう結果となることもございます。」
このように、直接的な「心象が悪い」よりも、ややマイルドで配慮のある表現がビジネスでは好まれます。
社内やフランクな場面で使う場合
同僚や社内チャットなどフランクなシーンでは、「心象が悪い」「印象が悪い」と率直に伝えても問題ありません。
しかし、目上の方や社外への連絡では敬意や配慮を持った言い換えを心がけると、信頼関係を損ねずに済みます。
「心象が悪い」を使う際の注意点とマナー
「心象が悪い」という言葉は、場合によっては主観的・断定的に聞こえることがあります。
ビジネス文書や会話では、できるだけ客観的でやわらかい表現を選ぶと、トラブルや反感を避けることができます。
感情的な表現になりすぎない工夫
たとえば、「心象が悪いのでやめてください」ではなく、
「誤解を招く恐れがございますので、別のご対応をご検討いただけますと幸いです。」
と伝えることで、指摘や要望も伝わりやすくなります。
相手の立場や状況にも配慮
「心象が悪い」と感じる理由や背景を添えることで、建設的なアドバイスや改善提案に変えることができます。
相手を責めるのではなく、前向きな言葉や提案をプラスするのもポイントです。
まとめ
「心象が悪い」は、心の中で受ける“良くない印象”や“違和感”を指す言葉です。
ビジネスでは「印象が良くない」「ご不快な思いをさせる」など、やわらかい言い換え表現を意識して使いましょう。
相手の立場や状況を配慮した伝え方で、良好なコミュニケーションを心がけてください。