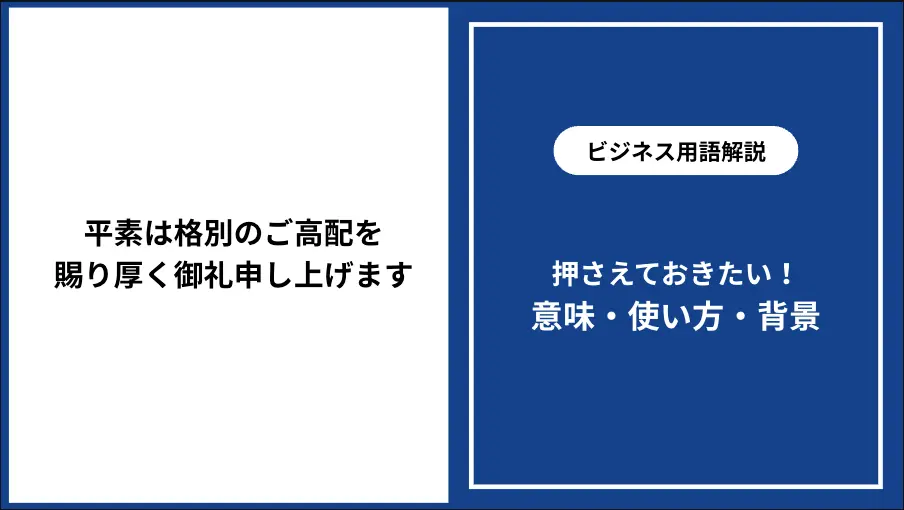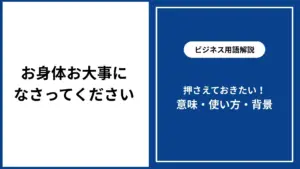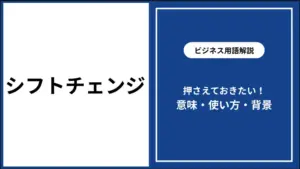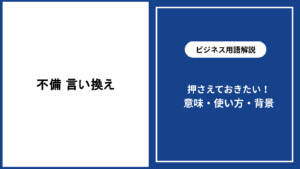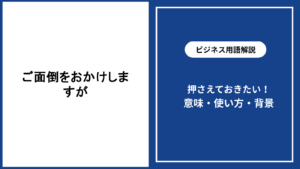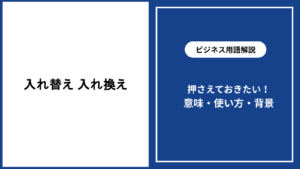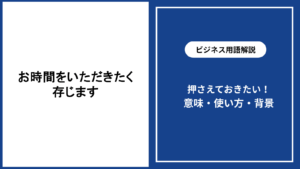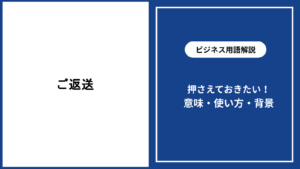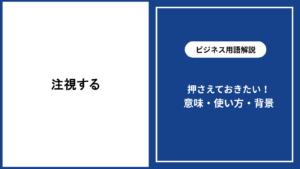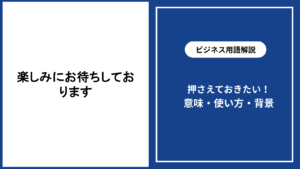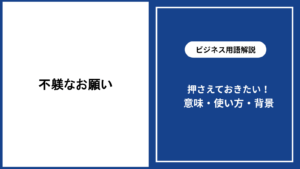「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」は、ビジネスメールや案内状などでよく使われる、とても丁寧な挨拶文です。
普段何気なく使っている方も多いですが、このフレーズには深い感謝と敬意が込められています。
この記事では、「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」の意味や成り立ち、正しい使い方、よくある例文、さらに似た表現との違いまで、詳しく解説します。
「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」の意味と成り立ち
「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」は、日頃から特別なご厚情・ご愛顧をいただいていることへの深い感謝の意を伝えるための定型句です。
非常にフォーマルな表現で、ビジネスシーンにおいて取引先や顧客、目上の方へのメールや文書の冒頭に使われます。
「平素」は「普段・日頃」を意味し、「格別のご高配」は「特別なご厚意、ご支援」という意味です。
「賜り」は「いただき」の謙譲語で、最後の「厚く御礼申し上げます」で深く感謝している気持ちを強調しています。
この一文だけで、相手への敬意と感謝の両方を丁寧に表現できます。
それぞれの言葉の意味と役割
・「平素」…普段、いつもという意味。ビジネスでは日常的な取引や支援への感謝を表します。
・「格別のご高配」…特別なご配慮、ご支援、特に深い厚意のこと。
・「賜り」…「いただく」の謙譲語で、相手から受けているというへりくだった言い方。
・「厚く御礼申し上げます」…心から深く感謝しています、という丁寧な感謝表現。
主な使用シーンと特徴
このフレーズは、取引先へのメールや案内状、請求書、契約更新のご案内、セミナー招待状など、フォーマルな文章の冒頭でほぼ必ず使用されます。
「いつもお世話になっております」よりさらに格式高く、儀礼的なニュアンスが強いため、改まったやりとりや文書に最適です。
また、季節の挨拶と組み合わせて使うことも一般的です。
例文で学ぶ使い方
・「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
・「平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。」
・「平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。」
どのパターンでも、文頭で相手への感謝を丁寧に伝えることができます。
| 表現 | 意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます | 普段から特別な配慮や支援を受けていることへの深い感謝 | とてもフォーマル。改まった書面やメールで使う |
| 平素よりご愛顧賜り、心より御礼申し上げます | 日常的なごひいき、ご支援への感謝 | ややカジュアルだが、十分丁寧 |
| いつもお世話になっております | 日常的なお付き合いへの感謝 | メール冒頭の一般的な挨拶。少しカジュアル |
似た表現・言い換えとその使い分け
「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」は、定型的なフォーマル表現ですが、場面や相手によっては別の表現を使うこともあります。
どのような違いがあるかを知っておくことで、より適切な文章作成ができます。
「ご愛顧」と「ご高配」の違い
「ご高配」は、目上の方や取引先、顧客などに対して使う最上級の敬語です。
一方「ご愛顧」は、お店やサービスなどで顧客からの支援やひいきに感謝する言い方で、やや親しみやすい印象です。
書類やフォーマルな案内状では「ご高配」、お礼状や店舗からの案内などでは「ご愛顧」がよく使われます。
メール・書類での使い方のコツ
・冒頭の一文として入れることで、文面が引き締まり丁寧な印象になります。
・季節の挨拶と組み合わせる場合は、「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて~」と次の内容に繋げます。
・何度も繰り返し使うと形式的な印象になるため、相手や文書内容によって「いつもお世話になっております」などと使い分けるのがおすすめです。
他の表現との使い分け例
・「平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。」
・「日頃より格別のお引き立てを賜り、心より感謝申し上げます。」
・「いつもご支援を賜り、誠にありがとうございます。」
相手や関係性、文書の目的に合わせて最適な表現を選びましょう。
| シーン | おすすめ表現 | 特徴 |
|---|---|---|
| 契約書・請求書・案内状 | 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます | 最も格式高い |
| DM・ニュースレター | 平素よりご愛顧賜り心より御礼申し上げます | 少しカジュアル、親しみやすい |
| 日常メール | いつもお世話になっております | 定番の挨拶。やや砕けた印象 |
まとめ|平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますの正しい使い方
「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」は、ビジネス文書やメールの冒頭で使われる最上級の敬意と感謝を込めた定型表現です。
相手への感謝や敬意を丁寧に伝えることができ、取引先や目上の方、顧客への文面に最適です。
意味や成り立ちをしっかり理解し、シーンや相手に合わせた使い分けを心がけることで、より信頼感のあるビジネスコミュニケーションが実現できます。