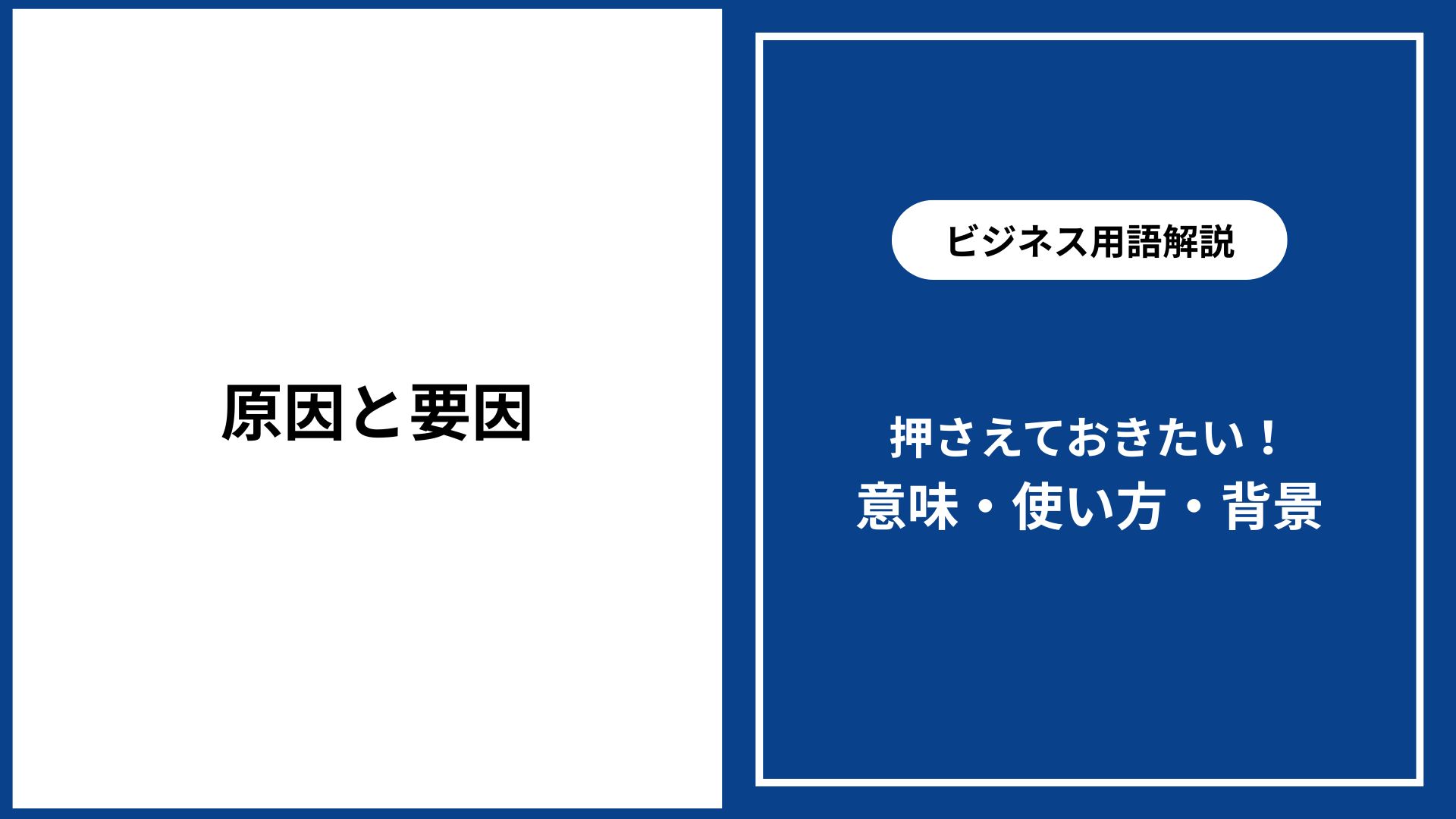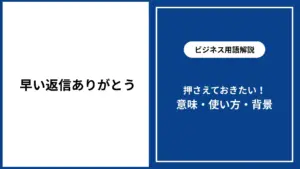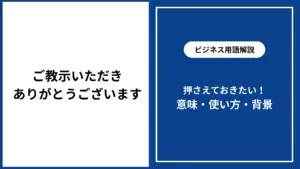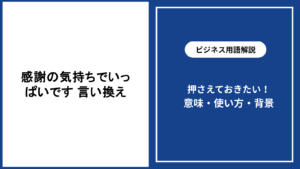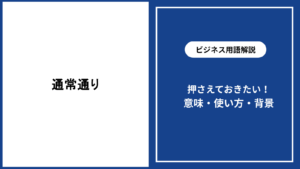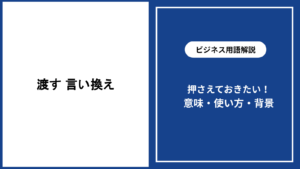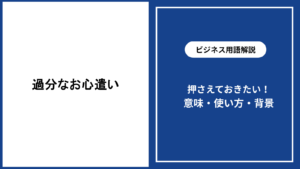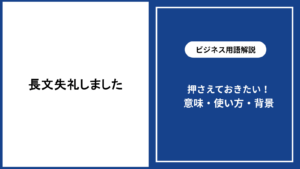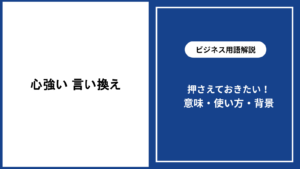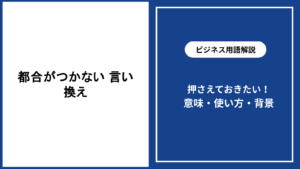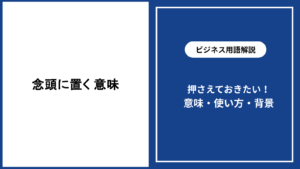「原因」と「要因」は、どちらも物事が起こるもとや理由を示す言葉ですが、実は使い方や意味に明確な違いがあります。
日常会話やビジネスシーンで使い分けられると、説明力や説得力が大きくアップします。
この記事では、「原因」と「要因」の違い・正しい使い分け方や、具体的な例文・類語との関係性まで詳しく解説します。
原因と要因の意味・定義の違い
まずはそれぞれの言葉の意味やニュアンスを明確に押さえましょう。
「原因」とは?
「原因」は、直接的に物事が起こるもとやきっかけを指す言葉です。
一つの出来事や結果に対して、一番大きな要素・直接的な引き金となるものが「原因」と呼ばれます。
たとえば「機械の故障の原因は部品の破損だった」「事故の原因は信号無視だった」など、はっきりと特定できる要素が該当します。
「要因」とは?
「要因」は、物事が起こるのに影響を与えた複数の要素や背景を示します。
「原因」が一つの引き金なら、「要因」は複数の間接的な要素が絡み合っている場合に使うことが多いです。
たとえば「売上減少の要因は、消費者動向の変化・新商品不足・広告予算の減少などが挙げられる」といったように、さまざまな背景・複数の影響が関わっている時に使われます。
簡単に言うと
・「原因」=直接的・主な引き金
・「要因」=間接的・複数の要素
この違いを意識するだけで、使い分けがしやすくなります。
原因と要因の使い分けポイントと具体例
それぞれの言葉をどのように使い分ければよいのか、実際のビジネスや日常の例で解説します。
ビジネスシーンでの使い分け例
例1:
・「プロジェクトの遅延の原因は、主要メンバーの退職でした。」
→「原因」は決定的な出来事や直接的な理由として使います。
例2:
・「プロジェクトの遅延の要因は、人員不足、情報共有の遅れ、工程の見直し不足などが考えられます。」
→「要因」は複数の背景や補助的な理由を並べて使います。
日常会話での使い分け例
・「風邪の原因はウイルス感染です。」
・「風邪をひきやすくなる要因には、疲労や睡眠不足、乾燥などがあります。」
このように、「原因」は最も直接的な理由に、「要因」は影響を与えるいろいろな環境や状況に使うのが適切です。
論理的な説明・分析での使い分け
プレゼンやレポートでは、「主な原因は〇〇だが、その他にも△△や□□といった要因が関係している」とまとめることで、全体像を分かりやすく説明できます。
「原因」と「要因」を明確に区別することで、説明がより論理的で説得力あるものになります。
原因・要因の類語・関連語と違い
「原因」と「要因」は似ていますが、他にも近い意味の言葉が多くあります。
それぞれの違いを押さえて、より的確に使い分けましょう。
「理由」との違い
「理由」は、物事が起こったり、行動をとったりする根拠や動機を広く表現する言葉です。
「原因」や「要因」は現象に焦点を当てるのに対し、「理由」は気持ちや動機にも使われます。
例:「退職の理由」「遅刻の理由」など、背景や動機を含むケースが多いです。
「動機」「背景」との違い
「動機」は、個人の内面的なきっかけに注目した言葉です。
「背景」は、現象を取り巻く広い状況や環境を指します。
「要因」は「背景」の一部ともいえる立ち位置で使われることが多いです。
「結果」との関係性
「原因」や「要因」があることで、「結果」が生じます。
この因果関係を正しく整理して説明することで、問題解決や説明責任を果たせます。
まとめ:原因と要因を正しく使い分けよう
「原因」は一つの直接的な引き金、「要因」は複数の間接的な影響要素という違いがあります。
場面や状況によって適切に使い分けることで、より分かりやすく、説得力ある説明や報告ができます。
ビジネスでも日常でも、この違いをしっかり理解して使いこなせるようにしましょう!