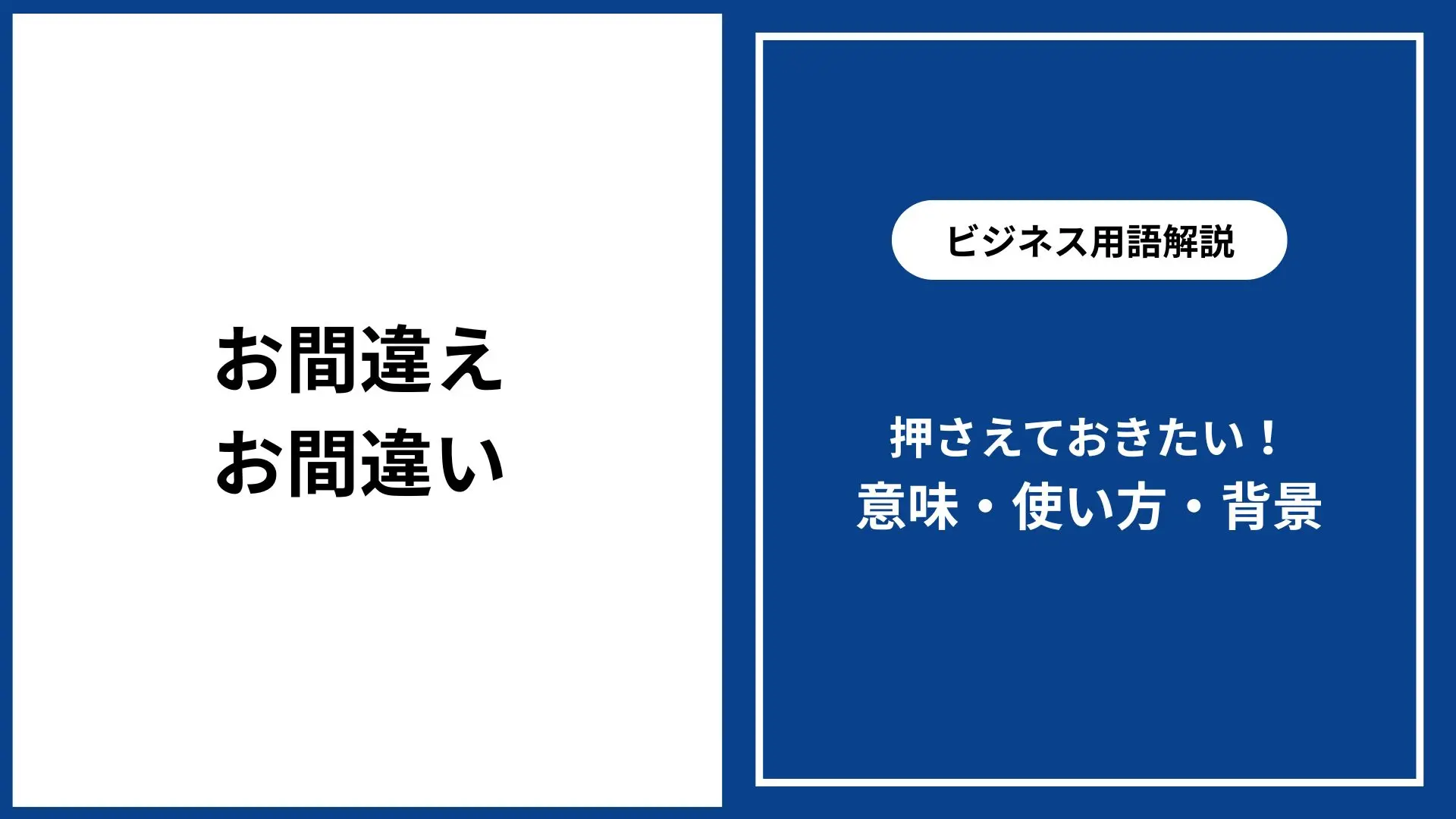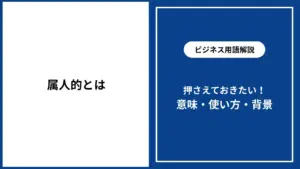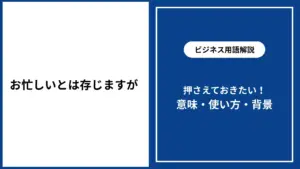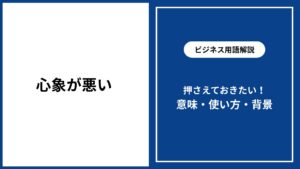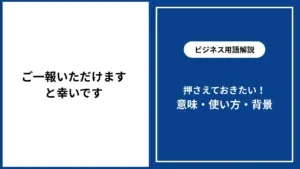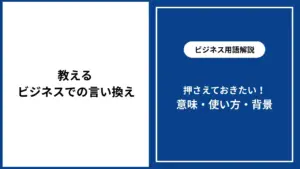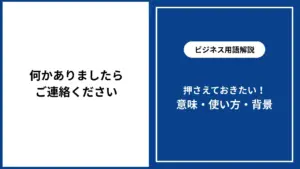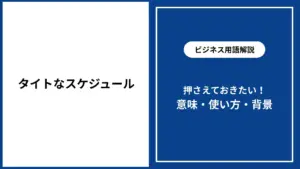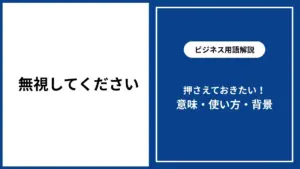「お間違え」と「お間違い」は、日常会話やビジネスシーンで使われることの多い表現ですが、
どちらが正しいのか、どう使い分ければよいのか迷う方も多い言葉です。
本記事では、それぞれの意味や使い方、ビジネスシーンでの正しい表現と注意点について詳しく解説します。
「お間違え」と「お間違い」の意味と違い
「お間違え」と「お間違い」は、どちらも「間違う」という動詞を丁寧にした表現ですが、
実は使い方や文法的な正しさに違いがあります。
「お間違い」は正しい敬語表現
「お間違い」は、「間違い」という名詞に丁寧語の接頭語「お」を付けたものです。
「お間違いありませんか」「お間違いのないようにご注意ください」など、ビジネスでもプライベートでも広く使われる自然な敬語表現です。
また、「お間違いでしたらお知らせください」のように使うこともできます。
「お間違え」は本来は不自然な表現
「お間違え」は、「間違える」という動詞の連用形「間違え」に接頭語「お」を付けたものですが、日本語としてはやや不自然な使い方です。
「お間違えありませんか」や「お間違えのないように」という形で使われることも見受けられますが、正しい敬語表現とは言いにくいため、
公式なビジネスシーンや書面では「お間違い」を使うのが無難です。
なぜ「お間違え」と言いたくなるのか
「間違え」という言葉は動詞「間違える」の連用形(動作や行為)なので、「お間違え」として丁寧にしたくなる気持ちは分かります。
しかし、日本語の敬語では「名詞+お(ご)」が基本です。
そのため「お間違い」の方が自然で、間違いなく丁寧な印象を与えられます。
ビジネスシーンでの正しい使い方・例文
ここでは、「お間違い」「お間違え」の正しい使い分けと、
実際のビジネスメールや案内文で使える例文を紹介します。
「お間違い」を使う場合
- お間違いありませんか
(例)「ご記入内容にお間違いがないかご確認ください。」 - お間違いのないように
(例)「ご来社の際は、お間違いのないようお気をつけください。」 - お間違いでしたらお知らせください
(例)「もしお間違いがございましたら、ご連絡くださいませ。」
「お間違い」は、安心して使える丁寧な日本語表現です。
「お間違え」を使いたいときの注意点
ビジネスメールや案内文では「お間違い」を使うことが推奨されますが、会話など口語的な場面では「お間違え」と言う人もいます。
ただし、正式な文書やメール、改まった場面では避け、「お間違い」を使う方が安心です。
使い分けのポイント
・公式な場面=「お間違い」が正解
・口語やフランクな会話で「お間違え」でも伝わるが、正しい敬語ではない
・悩んだら「お間違い」で統一
間違えやすい敬語・表現に注意しよう
日本語の敬語表現は、名詞化+「お(ご)」+適切な文型が基本です。
例えば、「ご確認」「ご連絡」「お知らせ」「ご記入」などと同じ感覚で「お間違い」を使うと間違いありません。
「お間違え」は避けるか、口語に限定しましょう。
間違えやすい表現の例
・「お伺い」→正しい
・「お伺え」→不自然
・「ご連絡」→正しい
・「ご連絡え」→不自然
このように、動詞の連用形に「お」を付けると違和感が出やすいので注意しましょう。
まとめ
「お間違え」と「お間違い」は似ていますが、正しい敬語表現としては「お間違い」が適切です。
公式なビジネス文書やメールでは「お間違い」を使い、間違えやすい敬語には十分注意しましょう。
日本語の美しい敬語表現を身につけ、ビジネスシーンでも自信を持って使えるようにしましょう。