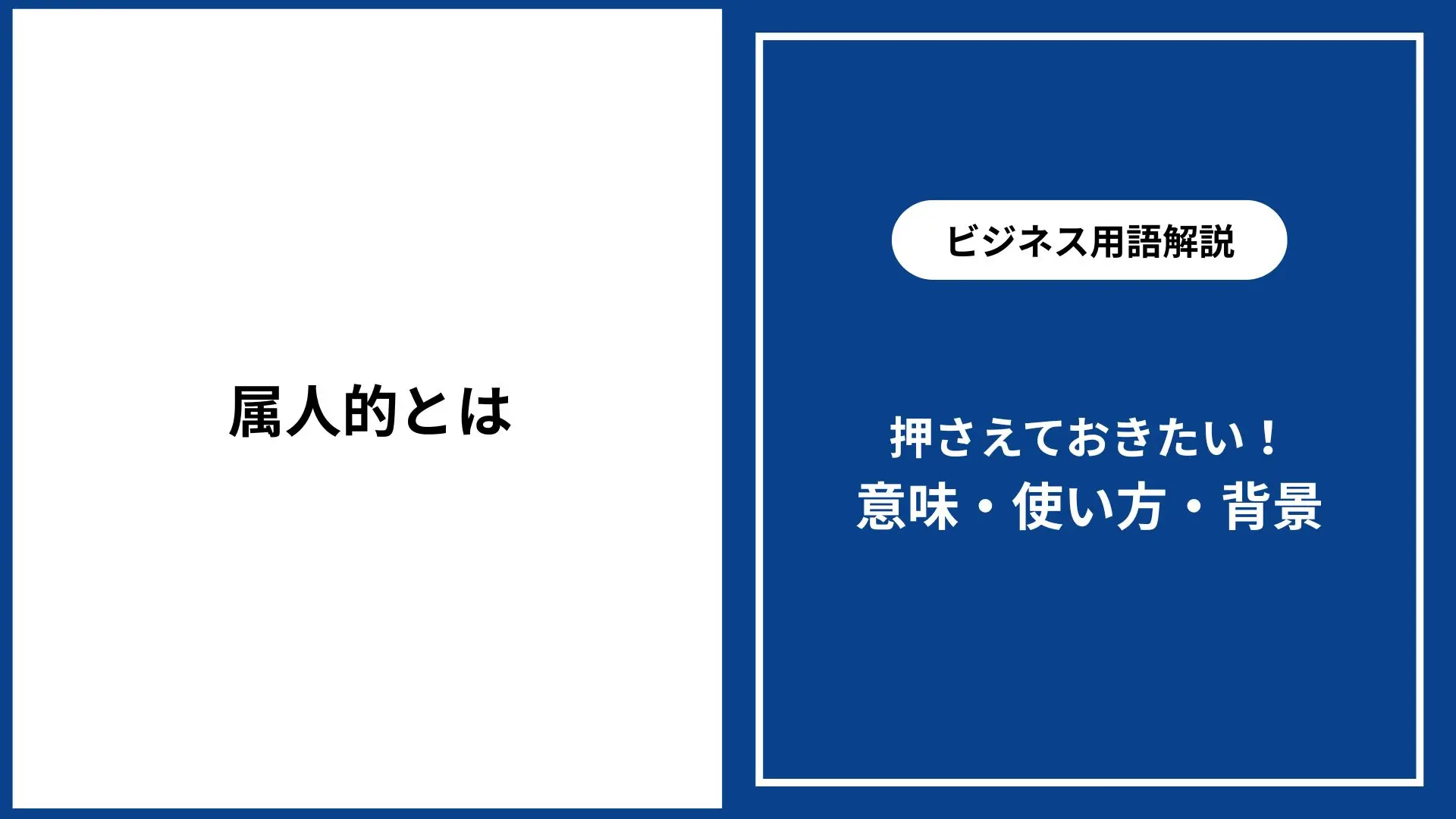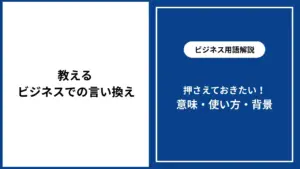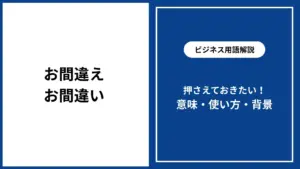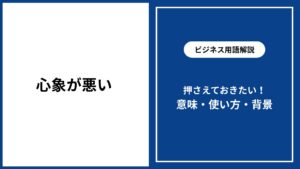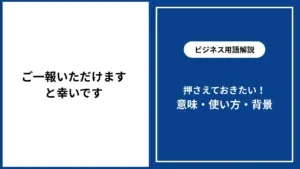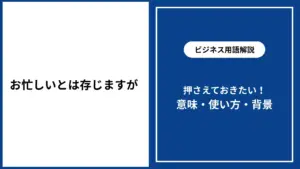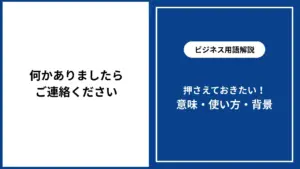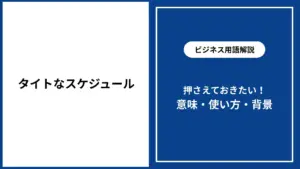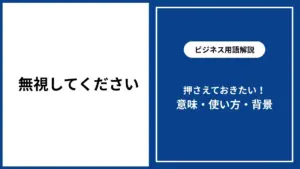「属人的」という言葉は、ビジネス現場や組織論、業務改善の文脈でよく使われる用語です。
日常会話ではあまり見かけませんが、働く人なら知っておきたい大切な意味と背景があります。
この記事では、「属人的」の正しい意味や使い方、ビジネスでの注意点や対策について詳しく解説します。
属人的とは何か?基本の意味と特徴
「属人的(ぞくじんてき)」とは、ある業務や仕事、運用などが特定の個人に依存している状態を指す言葉です。
「属人」とは「人に属する」という意味で、組織やチーム全体ではなく、個人の能力・経験・スキル・判断に大きく依存していることを表します。
例えば、「この業務は担当者がいないと進まない」「あの人にしかできない仕事」「彼のノウハウだけに頼っている状態」などが「属人的」な業務です。
なぜ「属人的」が問題視されるのか
属人的な業務は、業務の効率化や標準化、組織の安定運営という観点からしばしば課題となります。
特定の個人が休んだり退職したりした場合、その人以外に仕事を引き継げなかったり、対応できなかったりするリスクが高くなります。
また、業務のブラックボックス化や、情報共有の遅れも生まれやすいです。
属人的な業務の具体例
・担当者以外に詳細が分からない日次・月次処理
・特定の人の頭の中だけにある取引先情報やノウハウ
・マニュアル化や共有がされていない仕事
・ベテランだけが判断できる特殊な対応
このような状況は、属人的な運用・業務と言われます。
「属人的」の反対語・対義語
属人的の反対語は「標準化」や「仕組み化」「システム化」などです。
つまり、「個人に依存せず、誰でもできる状態にする」「組織としてノウハウや手順を共有する」ことが対策となります。
ビジネス現場での「属人的」な状況とその課題
ビジネス現場では、「属人的」な業務や体制はさまざまなリスクを生み出します。
ここでは、どんな場面で「属人的」が問題になるのか、実際の例やその影響について解説します。
属人的な業務が生まれる背景
属人的な業務は、急な業務拡大や人手不足、引き継ぎの不十分さ、属人的スキルに依存する風土などから生まれやすくなります。
ベテランの「自分がやった方が早い」という気持ちや、「忙しさでドキュメント化できていない」なども背景の一つです。
属人的な状態が招くデメリット
・担当者の不在で業務が止まる、ミスが発生する
・情報共有が進まず、組織全体の成長が遅れる
・引き継ぎや人材育成が進まない
・働き方改革・DX推進の妨げになる
属人的な運用が続くことで、人に頼る組織体質が固定化し、新しいチャレンジや業務効率化が進まないという弊害も生まれます。
属人的業務が発生しやすい業務領域
・経理や会計、総務などのバックオフィス業務
・営業の個別案件管理や人脈情報
・ITやシステム担当者の運用ノウハウ
・技術職や現場作業での“コツ”や“判断”
これらは特に属人的になりやすい領域と言われています。
「属人的」にならないための対策・改善策
属人的な業務を解消するには、仕組み化・標準化・マニュアル化が不可欠です。
組織全体で業務を「見える化」し、誰でも同じ水準で対応できるようにすることがポイントです。
主な対策・解決法
- 業務マニュアルや手順書の作成(属人的ノウハウを形式知に)
- 業務の見える化・情報共有(システムやクラウド利用)
- ジョブローテーションや多能工化(複数人で担当できる体制へ)
- 引き継ぎの徹底・定期的な業務棚卸し
- DXやITツールの導入による自動化
属人的業務を減らすことで、属人化リスクの低減・働き方改革・業務効率化など、多くのメリットが得られます。
属人的な業務から脱却するメリット
・業務が安定し、誰でも対応可能になる
・急な休職・退職でも組織が混乱しない
・教育や育成がしやすくなる
・働き方改革やリモートワークにも対応しやすい
「属人的」から「標準化」へ切り替えることは、強い組織づくりや人材育成にも直結します。
ビジネスでの「属人的」の使い方例
例1:
「この業務は属人的な運用になっているため、マニュアル化が必要です。」
例2:
「属人的な作業を減らして、誰でも対応できる体制を目指しましょう。」
例3:
「属人的な管理から脱却するために、業務の見える化を進めています。」
まとめ
「属人的」とは、特定の個人に依存した業務や運用を指し、ビジネスや組織運営の現場では大きな課題となります。
解決には、マニュアル化・標準化・業務の見える化が不可欠です。
「属人的な業務」から「誰でもできる体制」への移行を進めることで、強い組織と安定した業務運営が実現できます。