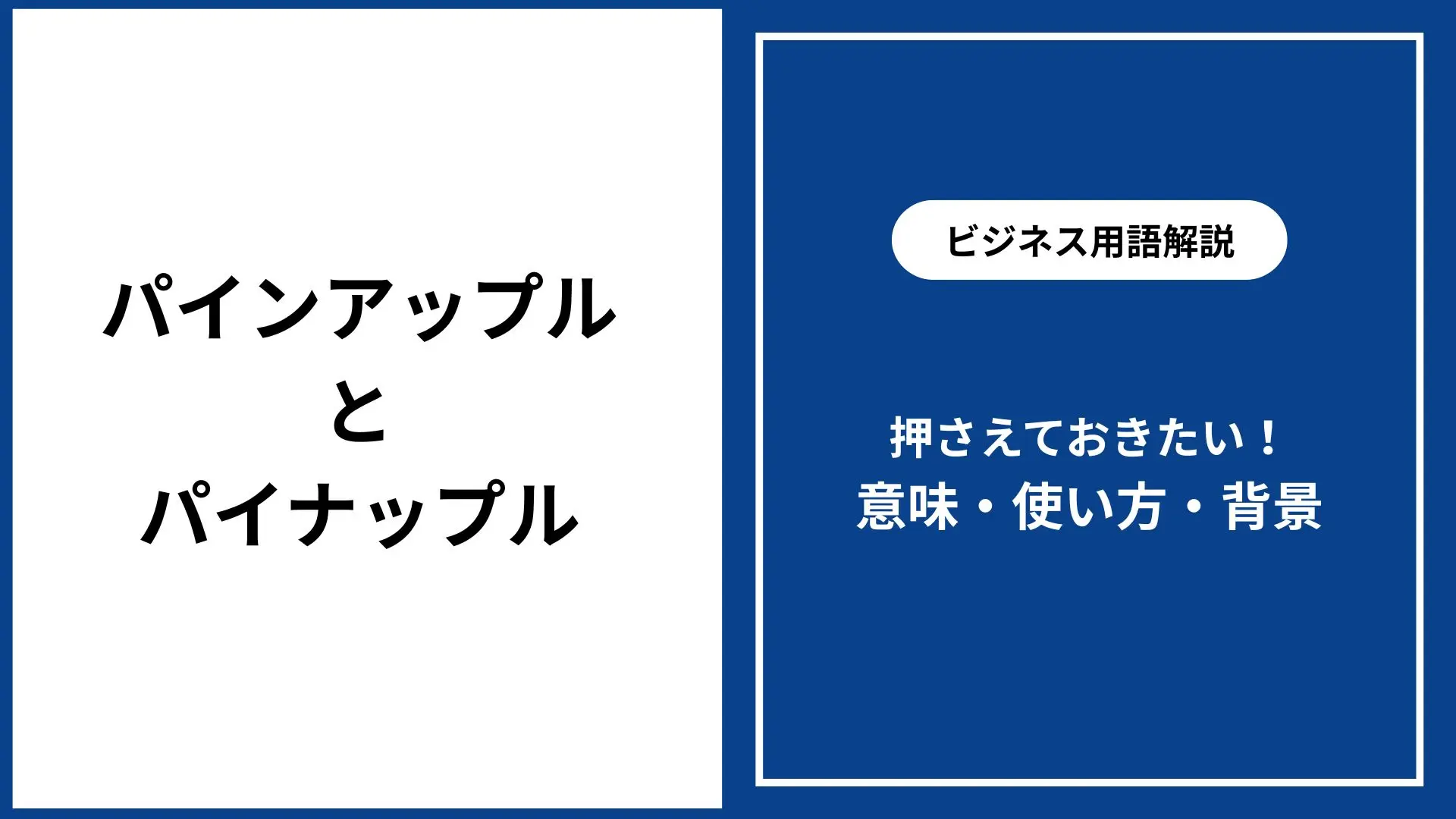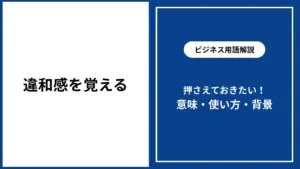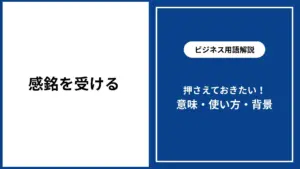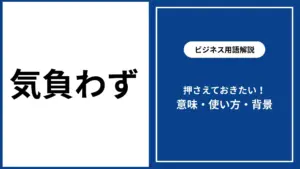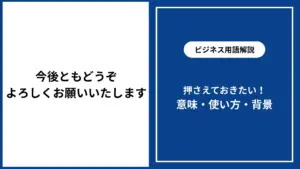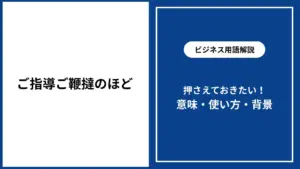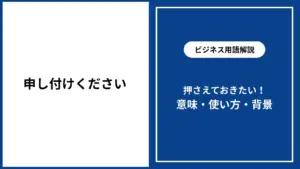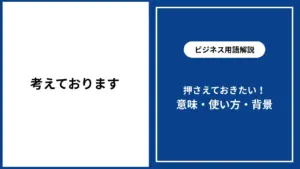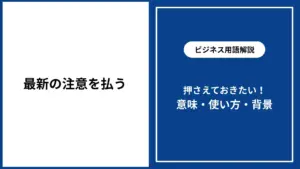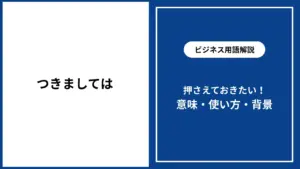「パインアップル」と「パイナップル」は、どちらもフルーツの「パイナップル」を指す言葉ですが、呼び方に違いがあることをご存じでしょうか?
この記事では、「パインアップル」と「パイナップル」の違いや意味、呼び方の由来、現代日本語での使い分けについて詳しく解説します。
ちょっとした雑学としても知っておくと会話が弾む内容です。
パインアップルとパイナップルの違いとは?
「パインアップル」と「パイナップル」は、どちらも同じフルーツ(Pineapple)を指す言葉ですが、呼び方や使われ方に違いがあります。
「パイナップル」は現代日本語で最も一般的な呼び方で、スーパーやレストラン、日常会話ではほぼ「パイナップル」と表記・発音されます。
一方、「パインアップル」は主に明治時代~昭和初期の古い日本語表記・発音で、現在では缶詰商品や一部の業界用語、古い文献などで目にすることがあります。
語源・呼び方の由来
どちらも英語の「Pineapple(パインアッポー)」が語源です。
日本には明治時代にこのフルーツが伝わり、最初は英語の発音に近い「パインアップル(パイン・アッポー)」と呼ばれていました。
しかし、時代が進むにつれ、日本語の音韻に馴染みやすい「パイナップル」という呼び方が普及し、現在はこの表記が標準となっています。
現代での使い分けと実際の使われ方
「パイナップル」は、一般的な会話・流通・飲食店・学校教育などで使用される標準的な名称です。
缶詰やジュースなどの商品名、パッケージ、メニューでもほとんどが「パイナップル」と書かれています。
一方、「パインアップル」は、古い商品名・老舗ブランド・業界用語として残っていたり、歴史的資料や昭和のレシピ本などで見かける場合があります。
例えば「パインアップル缶詰」「パインアップルジュース」など、レトロな響きを意識したネーミングや、特定のブランド名に使われるケースが見られます。
誤用・混同の心配は?
どちらの呼び方も誤りではありませんが、現代日本語では「パイナップル」が正規表現として通用します。
「パインアップル」を使っても意味は通じますが、やや古風・懐かしい印象を与えます。
公的な文書や学校教育、一般的な商品名には「パイナップル」を使うのが一般的です。
パインアップルとパイナップルの類語・関連表現
どちらも「Pineapple」の日本語表記なので、基本的に意味の違いはありません。
類語として「鳳梨(ほうり)」という漢語表現もありますが、これは中国語や漢字表記の際に用いられるもので、日常会話ではほぼ使われません。
英語発音との違い
英語の発音は「パインアッポー」に近く、日本語ではそれが「パイナップル」として定着しました。
古い時代の表記や商品名、看板などで「パインアップル」が残っているのは、その名残です。
まとめ:パインアップルとパイナップルの違いと使い分け
「パインアップル」と「パイナップル」は、どちらも同じフルーツを指しますが、現代では「パイナップル」が主流の呼び方です。
「パインアップル」は古い表記やレトロなイメージ、特定のブランドや商品で見られることがあります。
意味の違いはありませんが、シーンに応じて使い分けるとより自然なコミュニケーションができます。