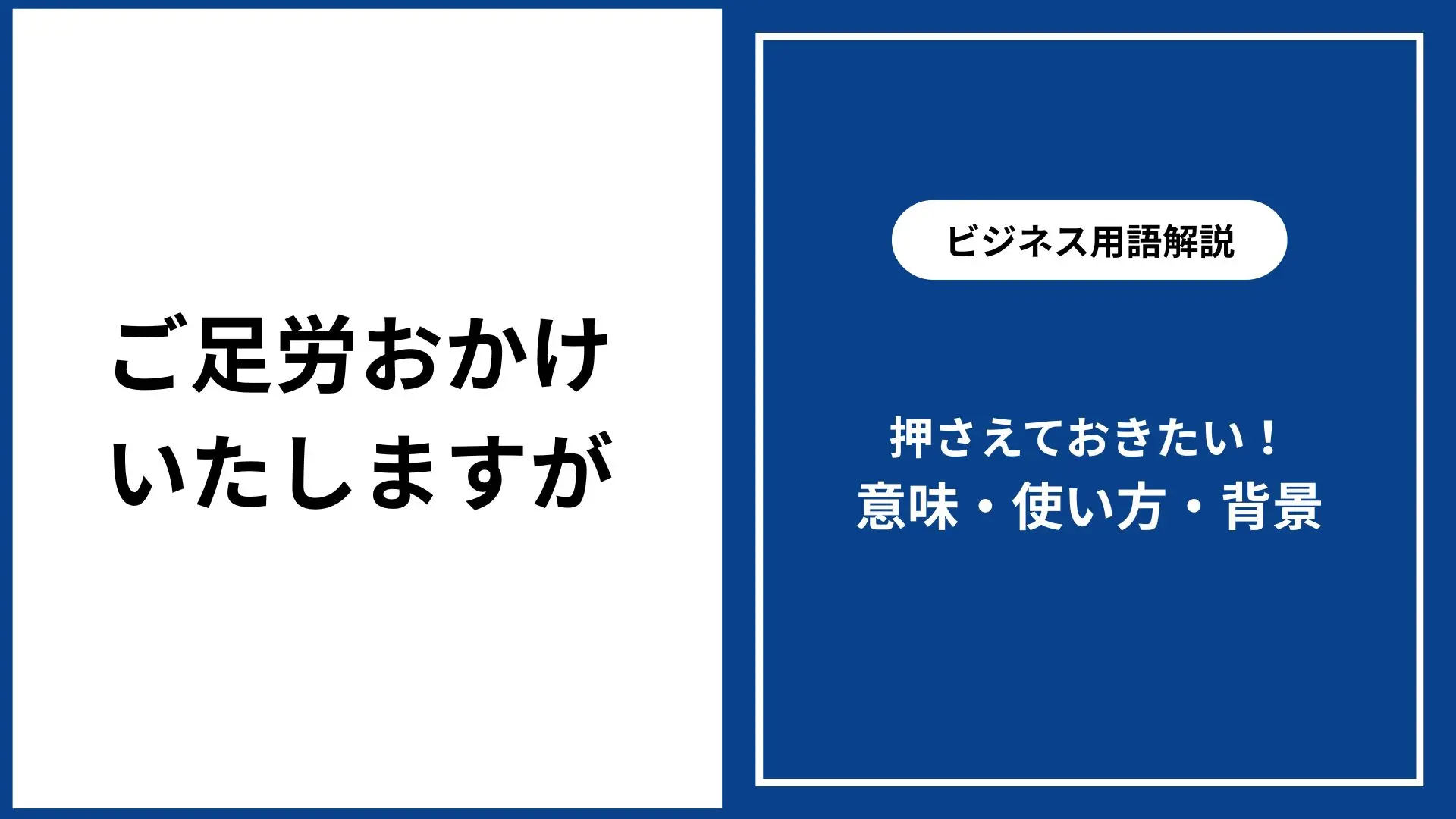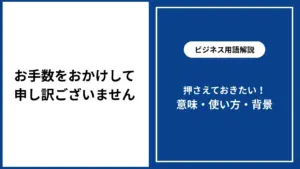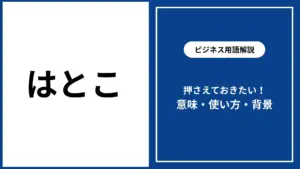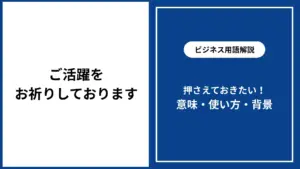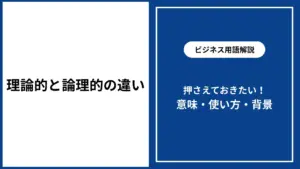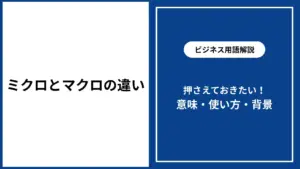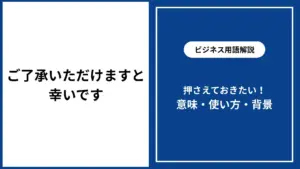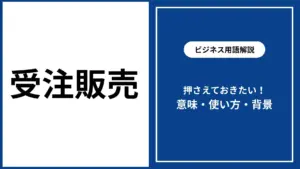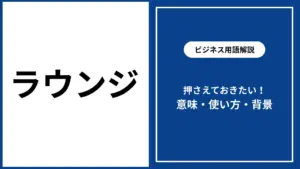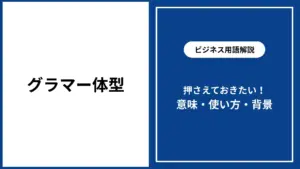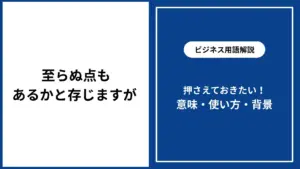「ご足労おかけいたしますが」は、相手にわざわざ来てもらう際の恐縮と感謝を同時に伝える日本語敬語表現です。
ビジネスやフォーマルな場面で頻出する一方、正確な意味や適切な使い方を知らないと失礼になりかねません。
この記事では語源から具体例、類語比較、英語訳まで余すところなく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
「ご足労おかけいたしますが」の意味
まずはこのフレーズが持つ本来の意味を確認し、敬語としての位置づけを理解しましょう。
語源と成り立ち
「ご足労おかけいたしますが」は足労という名詞に丁寧語の接頭辞ごを加え、相手の行動に負担をかける意を示す補助動詞おかけするを用いた表現です。
古語の「労(らう)」は「苦労・骨折り」を意味し、「足労」は「足を使った労苦」、すなわち「わざわざ来る手間」を指します。
江戸期の書簡にはすでに用例が見られ、主に商家が取引先や顧客に対して使ったとされます。
この歴史的背景から、現代でも取引先や顧客など目上・社外への依頼表現として根強く使われています。
補助動詞「おかけする」は謙譲語であり、「相手に負担をかけることへの詫び」を示します。
そのため「ご足労おかけいたしますが」は単なる「来てください」ではなく、「申し訳ないがわざわざ来ていただけますか」という恐縮+感謝の二重敬語的ニュアンスを帯びています。
なお、現代語の敬語体系では二重敬語を避ける場合も多いものの、この表現は慣用句として定着しているため違和感なく用いられます。
敬語表現としての特徴
このフレーズは敬語三分類で謙譲語Ⅰに該当します。
話し手が自分の行為(相手に来てもらうお願い)をへりくだることで、相手の立場を高める働きをします。
同じ依頼表現「お越しいただけますでしょうか」よりも負担に対する謝罪が強調される点が特徴です。
また、ビジネスメールや対面の商談など、フォーマル度が高いシーンでは相手の労力への配慮を言語化することで信頼感を醸成します。
敬語の重複を避けたい場合は「ご足労いただきありがとうございます」「ご足労をおかけしますが」など形を崩しても意味は保たれます。
ただし口頭では語勢がやや硬いので、柔らかいトーンを出すなら後述の言い換え表現を併用すると良いでしょう。
「恐れ入りますが」との違い
似た場面で使われる恐れ入りますがは、依頼や謝罪の前置きとして「恐縮」の気持ちを表す前置き句です。
一方「ご足労おかけいたしますが」は「恐れ入ります」に「足を運んでもらう負担」を明示する点で限定的かつ具体的です。
仮に電話で用いる場合、実際に足を運ぶ必要がないなら「ご足労~」は不適切で「恐れ入りますが」を選ぶのが自然です。
また「恐れ入りますが」は物理的移動を伴わない依頼(資料送付・情報提供など)にも汎用的に使えますが、「ご足労~」は対面前提のシーンに限定される点に留意しましょう。
従って「恐れ入りますが、書類をご確認ください」とは言えても、「ご足労おかけいたしますが、書類をご確認ください」は文脈が合わず違和感が生じます。
使い方と場面別例文
ここでは実際の業務や日常生活でどのように用いるか、シチュエーション別に詳しく見ていきます。
ビジネスシーン
商談アポイントでは「本日はご足労おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします」と開会時に述べると、客先への敬意と感謝が明瞭に伝わります。
会議室変更などで取引先を別フロアへ案内する際も「急なご足労をおかけいたしますが、○階へご移動願えますでしょうか」と言えば配慮が行き届いた印象です。
また、研修講師を依頼するときに「遠方よりご足労おかけいたしますが、ご講演のほどお願い申し上げます」と添えると丁重さが際立ちます。
このように物理的移動を伴う依頼や感謝にセットで用いることで、相手への配慮と尊重が同時に叶います。
さらに社内メールの冒頭で「本日はご足労おかけいたしますが、ご協力のほどお願いいたします」と書くと、社外だけでなく上司・先輩にも丁寧に響きます。
目上の人・顧客への配慮
役員クラスを本社へ招く場合には「お忙しい中ご足労おかけいたしますが、ご来社賜りますようお願い申し上げます」と格式張った表現を採用します。
BtoB取引で工場見学を設定する際も「遠方よりご足労をおかけいたしますが、弊社拠点にて実機をご覧いただければ幸いです」と伝えると真摯な姿勢が伝わります。
また、謝罪訪問をお願いするケースでは「大変恐縮ではございますが、ご足労おかけいたしますが、一度お時間を頂戴できませんでしょうか」と用いて負担を強く意識していることを示しましょう。
顧客アンケートの回収を対面で行う際などにも「ご足労おかけしますが、ご協力お願いいたします」と添えることで、顧客の時間的コストを軽減しきれない点への謝意を示せます。
メール・文書での書き方
メールの場合、件名に「ご来社のお願い(ご足労おかけいたしますが)」と入れると本文を読まずとも要件が理解され、配慮が伝わります。
本文では冒頭または締めで用いるのが定石で、冗長にならないよう1メール1回を目安にしましょう。
文末例:「ご足労おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。」
敬称や日付と組み合わせる際は「○○様 いつもお世話になっております。
早速で恐縮ですが、ご足労おかけいたしますが、下記日程にてご来社いただけますと幸いです。」と配置すると読みやすさが向上します。
類語・言い換え・英語表現
最後に表現のバリエーションを広げるため、似た日本語や英語でのニュアンスの違いを確認しておきましょう。
近しい日本語敬語との比較
「お越しいただけますでしょうか」は移動の事実を丁重に依頼する表現で、負担への謝罪要素は弱いものの汎用性が高いです。
「ご足労願います」はやや古風で省略形ですが、現場作業員へ丁寧に指示する際など硬めの文書で重宝します。
「ご足労おかけすることとなり恐縮ですが」とクッション言葉を挟むと柔和な印象を与えつつ丁重さを保てます。
これらはいずれも謙譲語ですが、謝意・恐縮・依頼の度合いを微調整して使い分けることで文章・会話がぐっと洗練されます。
カジュアルな言い換え
社員同士のフラットな関係では「わざわざ来ていただく形になってしまいますが~」のように日常的な言い回しで負担を示すことも可能です。
顧客ユーザーに対してチャットサポートで使う場合は「お手数をおかけしますが、直接お越しいただけますか?」とお手数を用いると柔らかさが出ます。
また、イベント集客メールでは「ご足労とは存じますが、ご来場いただければ幸いです」と書くとフォーマルさを保ちつつも親しみやすさが漂います。
英語でのニュアンス
英語圏で類似の丁寧表現に当たるのは「We apologize for the inconvenience of asking you to come」「Sorry to trouble you, but could you visit us?」などです。
「足を運ぶ労力」そのものを示す語が英語に直接は存在しないため、「inconvenience」「trouble」など抽象語で代替し、文脈で補います。
メール結びでは「We appreciate your taking the time to come all the way to our office.」と感謝の意を明確にすると、日本語の「ご足労おかけいたしますが」に匹敵する丁寧さが演出できます。
なお直訳で「foot labor」を用いると不自然なため避けましょう。
まとめ
ご足労おかけいたしますがは、相手の移動という負担を明示的に認めつつ依頼する、日本語敬語ならではの繊細な表現です。
語源を紐解けば「足労=足を使う労苦」への謝意が核にあり、敬語構造としては謙譲語的な謝罪+依頼の複合句となっています。
ビジネス・フォーマルシーンでは場面や相手に応じて「恐れ入りますが」「お越しいただけますでしょうか」などと使い分け、メールや対面での印象を最適化しましょう。
英語では直訳せず「inconvenience」や「trouble」を用いることで同等のニュアンスを表現可能です。
本記事を参考に、相手への敬意と感謝を文字に託すコミュニケーションスキルを磨いてみてください。